- 日本零売薬局協会が解散。厚生労働省の規制強化によるもの(2024/7/11)
- 非方箋医薬品を販売する「零売」に対し、2024年は具体的なガイドラインが示される予定(2024/4/3)
- 非方箋医薬品を販売する「零売」の見直しについて「医薬品の販売制度に関する検討会」のとりまとめ(2024/1/18)
- 非方箋医薬品を販売する「零売」の見直しについて方向性が厚生労働省で大筋了承される(2023/12/20)
- 非処方箋医薬品を販売する「零売」の見直しに関する検討会にて「漢方」のOTC薬販売を厚生労働省がメーカーへ要請(2023/10/31)
- 非処方箋医薬品を販売する「零売」を維持すべき!(保険薬局経営者連合が反発)
- 非処方箋医薬品を販売する「零売」についての日本薬剤師会会長の見解(2023/9/19)
- 非処方箋医薬品を販売する「やむを得ない場合」の例と要件(2023/9/9)
- 非処方箋医薬品を販売する零売薬局は事実上、解体か?(2023/8/7)
- 「処方箋がなくても病院の薬が買える」は不適切な表現である(20228/11)
日本零売薬局協会が解散。厚生労働省の規制強化によるもの(2024/7/11)
非処方箋医薬品の販売を普及することを目的として、2020年に設立された「日本零売薬局協会」が解散しました。
厚生労働省による「零売」への規制を強化したことや、日本零売薬局協会の中核だった「GOOD AID」がファーマライズホールディングスの子会社となったことが要因のようです。
同協会は2021年に零売の手順などの定めたガイドラインを公表し、非処方箋医薬品の医療における選択肢を提示していました。
非処方箋医薬品の販売に関しては、2024年から2025年にかけて、法令が整備される見通しとなっており、事実上「零売」が厳しい状況となることが解散の本質のようです。
非方箋医薬品を販売する「零売」に対し、2024年は具体的なガイドラインが示される予定(2024/4/3)
日本医師会常任理事の宮川氏は2024年3月31日の日本医師会臨時代議員会にて零売薬局について以下のように言及しました
「本来の目的から逸脱した処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売であり、重大な問題」
また、「2024年には零売はやむを得ない場合に認め、零売を薬局の特徴として強調する広告の禁止などの法改正を行い、具体的なガイドラインが示される予定であると」説明しましあ。不適切な零売があれば、各都道府県の担当課や日医に報告するよう求めています。
「医療用医薬品の販売は、処方箋による販売を基本とし、災害時など非常に限定された事態を想定して、正当な理由がある場合、やむを得ない場合において、薬局で販売を認める形になった。また、一般消費者向けに医療用医薬品が販売可能である零売を薬局の特徴として強調する内容の報告に関しては、不適切であるから禁止すべきということが示された。既に本検討会における議論を受けて、零売専門薬局チェーンが撤退を表明、業態を転換する動きがある」。
と述べています。
非方箋医薬品を販売する「零売」の見直しについて「医薬品の販売制度に関する検討会」のとりまとめ(2024/1/18)
厚生労働省は2024年1月12日に、「医薬品の販売制度に関する検討会」の取りまとめを公表しました。
・濫用等の恐れのある医薬品の販売では小容量1個を原則として20歳未満には複数個・大容量を販売しないこと
・法令上、非処方箋医薬品は「やむを得ない場合」での販売を認める
薬局での販売に当たっては、最小限度の数量とし、原則として、当該患者の状況を把握している薬局が対応することとし、薬歴の確認や販売状況等の記録を必要とする。
*やむを得ない場合
①医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合であって、一般用医薬品で代用できない場合
②社会情勢の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売
することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合
非方箋医薬品を販売する「零売」の見直しについて方向性が厚生労働省で大筋了承される(2023/12/20)
非方箋医薬品を販売する「零売」の見直しについて、厚生労働省は「医薬品の販売制度に関する検討会」を2023年12月18日に行い、2025年にも行う医薬品医療機器等法の改正に向けて、大筋で方向性が了承されました。
零売に関しては、処方箋なしで医療用医薬品が買える薬局の販売規模が拡大しており、日常的な販売や不適切な販売方法の広告が継続されていることを問題視し、「医療用医薬品は処方箋に基づく交付が基本」「やむを得ない場合」については具体的な例示を含めてガイドラインで整理するとしました。
また、乱用のおそれのある医薬品の販売に関しては、対面かオンラインでの販売を原則にする。20歳以上が小容量の製品1個のみ購入しようとする場合は、対面かオンライン以外の販売も可能。
原則1人1包装単位の販売にする。特に20歳未満が購入を希望する場合には小容量の製品1個の販売のみとする。
一般用医薬品の区分に関しては、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の2区分にする。
非処方箋医薬品を販売する「零売」の見直しに関する検討会にて「漢方」のOTC薬販売を厚生労働省がメーカーへ要請(2023/10/31)
2023年10月30日、第9回医薬品の販売制度に関する検討会が行われ、非処方箋医薬品の販売の在り方に関する対応案が開示されました。
以下に概要を記します。
医療用医薬品(処方箋医薬品を除く)は例外的に「やむを得ない場合」について薬局で販売を認めることを法令上に規定する
「やむを得ない場合」
(1)
・医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合
・ OTC医薬品で代用できない、又は代用可能と考えられるOTC医薬品が容易に入手できない場合
上記のいずれもを満たす場合と記されています。
(2)
社会情勢の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合
という記載もありますが、こちらの要件はいわゆる「災害時」といったところでしょうか。実際的には(1)が「やむを得ない場合」の要件と考えます。
「やむを得ない場合」における販売要件
(1)原則として、必要としている医薬品を調剤した薬局や、継続して処方箋を応需するなど、当該患者の状況を把握している薬局が販売すること(旅行先にいる等、通常利用している薬局の利用が難しい場合等の例外的な場合を除く。なお、例外的な場合に販売を行う薬局は、薬歴を適切に管理して確認できることを条件とし、通常利用している薬局(必要となった医薬品を調剤した薬局)に連絡を取り、連携を図るこ と。)。なお、患者の状況を把握し、処方した医療機関と連携すること が重要であるという観点から、かかりつけの薬剤師・薬局であることが望ましい。
(2)一時的に(反復・継続的に販売しない)、最小限度の量(事象発生時には休診日等で行けない、当該疾患で通常受診している医療機関に受診するまでの間に必要な分、最大で数日分等)に限り販売すること。
(3)適正な販売のために購入者の氏名、販売の状況等を記録すること。 (1)の場合は受診している医療機関に情報提供すること。
つまり、「やむを得ない場合」は継続的に処方箋調剤を行っている薬局が必要最小限を販売し、医療機関へ情報提供することが求められるという対策案となり、至極まっとうな要件に感じます。
尚、漢方薬・生薬については、医療用医薬品の製品しか製造販売されていない漢方製剤・生薬製剤があるが、これらについて
① 「薬局製造販売医薬品」の範囲の見直し(拡大)の検討
② 医療用医薬品の漢方製剤を製造販売しているメーカーに働きかける
ということで、厚生労働省の方針として、漢方薬は「OTC」での販売拡大を進める方針のようです。
非処方箋医薬品を販売する「零売」を維持すべき!(保険薬局経営者連合が反発)
保険薬局経営者連合(薬経連)は2023年9月14日、非処方箋医薬品の販売(零売)について、国が規制強化を検討していることに対して反発する見解を示しました。
「慎重な議論を期待する」
「患者が希望する零売を規制することは、消費者の利便性を根拠に薬局の規制緩和を繰り返したこれまでの政策とは「一貫性を欠く」
「自分たちの世代では可能だったことを将来の薬局では不可能にするような選択を軽々しくすべきではない」
「制度の趣旨と運用の実態が乖離しているのであれば、制度の趣旨を実態に合わせることがあっても良いのではないか」
として、これまで通り「零売」を続けられるよう見解を示しました。
大変恐縮ですが、私は保険薬局経営者連合を存じ上げませんでした。
私の個人的な感想なのですが、保険薬局経営者連合のホームページをみて役員名簿を見てみたのですが、この連合の会員は「保険薬局業を営む法人または準ずる個人」と記載されていますので、いわゆる”「個人薬局」の集まり”なのでしょうかね。
厚生労働省や医師会・薬剤師会が「零売は中止しましょう」という流れを構築している現在において、保険薬局経営者連合が立ち向かっている構図ですね。
保険薬局経営者連合からすると、大きな壁に立ち向かうような戦いなのかもしれませんが、民主主義の日本ですので、自分の意見を掲げることは素敵なことだと思います。
2023年9月16日、日本薬剤師会の都道府県か会長協議会が行われ、「日本薬剤師会政策提言2022」の改訂版を公表されました。
その中に「医療用一般用医薬品(仮称)類型の創設」という提言項目がありました。
医療用一般用医薬品(仮称)とは、地域住民が医薬品をより活用しやすくするため、医師と薬剤師の両者で対応することができる一般用医薬品(OTC医薬品)の新たな類型として日本薬剤師会が提案していく方針としています。
医療用医薬品を処方箋なしで販売する「零売」とは異なる新たな仕組みとして、医療用一般用医薬品とは医師による処方でも交付できるし、薬局で販売することもできる新たな類型と考えているそうです・・・・
現在、厚生労働省が零売のありかたについて、通知による規制ではなく「法令」上として位置付ける方向で話し合いを行っているわけですが、法令で定められてしまうと、日本薬剤師会が提言しようとしている「医療用一般用医薬品」という枠組みは水に流されてしまうような気がします。
非処方箋医薬品を販売する「零売」についての日本薬剤師会会長の見解(2023/9/19)
日本薬剤師会会長の山本信夫氏が2023年9月16日に行われた都道府県会長協議会にて挨拶を行い「零売について」の見解を示しました。
「いき過ぎてしまったと指摘を受けているいわゆる零売薬局」について、医薬品販売制度に関する検討会で議論されていることを指摘しました。
また、
「まもなく報告が出ると思う」「慎重な議論が進んでいる」との見方を示しました。
「そもそも零売の持っている機能、所期の目的を損なわないように、一方で行き過ぎた零売行為が横行しないように慎重な議論が進められている」と述べました。
これまで、同会長の見解としては
2023年8月9日(会見)
処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売(零売)の規制案について「過剰な規制内容だとは思っていない:
「原則かかりつけ薬局の対応」などの零売条件の追加案について「今までの通知の内容とそれほど大きな差はない」
と言及しつつも「どの程度の量を販売するか、また販売しないかというのは薬剤師の判断によるものであるべきで、そこは変えてほしくない」とも述べていました。
零売専門薬局に対しては「(法令や通知に)書かれていないからやってもいいというのは、薬剤師ではない」と断じていました。
2023年6月24日(定時総会演述)
「やみくもに零売を規制するかどうかという議論は本質を見誤った議論」
「必要以上の規制が設けられるような事態にならぬよう積極的に意見を主張していかなくてはならない」との考えを示しています。
「零売行為を拡大解釈し、専ら医療用医薬品の販売を主体とする、およそ薬局とは言い難い特殊な販売形態を取る薬局が散見されている」と指摘していました。
非処方箋医薬品を販売する「やむを得ない場合」の例と要件(2023/9/9)
非処方箋医薬品を販売する場合における「やむを得ない場合」の例として以下の①、②のいずれも満たす場合が提案されました。
① 医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合
② OTC医薬品で代用できない、もしくは、代用可能と考えられるOTC医薬品が容易に入手できない場合(例えば、当該薬局及び近隣の薬局等において在庫がない等)
(2)社会情勢の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合
○ 上記「やむを得ない場合」における販売に当たっては、次の要件を課すよう整理してはどうか。
(1)原則として継続して処方箋を応需する等、当該患者の状況を把握している薬局が販売すること(旅行先等通常利用している薬局の利用が難しい場合等の例外的な場合を除く。なお、例外的な場合に販売を行う薬局は、通常利用している薬局(必要となった医薬品を調剤した薬局)に連絡を取り、連携を図ること)。
(2)一時的に(反復・継続的に販売しない)、最小限度の量(事象発生時には休診日等で行けない、当該疾患で通常受診している医療機関に受診するまでの間に必要な分、最大で数日分等)に限り販売すること。
(3)適正な販売のために購入者の氏名、販売の状況等を記録すること。(1)の場合は受診している医療機関に情報提供すること。
上記のルールが現時点における「案」ですが、このルールが法令上明記されれば「零売薬局」は解体となるでしょう。
また、一般用医薬品(OTC医薬品)に関しては、これまでの「第1類、第2類、第3類」という分類を廃止し、「薬剤師が販売する医薬品」「薬剤師又は登録販売者が販売する医薬品」
という2つの分類に分けられることが提案されています。
非処方箋医薬品を販売する零売薬局は事実上、解体か?(2023/8/7)
厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」が2023年8月4日に行われました。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品を患者へ直接販売する(零売)について議論が行われ、零売のルールとされていた「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」という分類を失くす方向で話し合いが行われ、おおむね了承されました。
今後、法律上での医薬品の分類として「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」という分類がなくなった場合、医療用医薬品は原則として「医師の処方に基づく販売」のみとなります。
ただし、例外として「やむを得ない場合は販売が可能」という例外措置も設けられており、資料には「処方箋なしで販売の求めがあると想定される事例」としていくつか要求事例とその対応が提案されていました。「やむを得ない場合」に「薬局での販売を認める」としつつ、災害時以外の対応としては以下の要件が求められます。
①医師に処方され服用している医療用薬が不測の事態で手元にない状況となり、かつ診療を受けられない場合
②一般薬で代用できない、代用可能と考えられる一般薬が容易に入手できない場合
上記のケースにおいて、販売は原則「かかりつけ薬局」として厳格な可否判断を求め、販売記録や医療機関への報告などを要件に設定する方針としています。
薬局による医療用医薬品の販売については、例外性がより強化されるため、事実上、零売は難しい状況となります。
「処方箋がなくても病院の薬が買える」は不適切な表現である(20228/11)
追記:零売は「法律上の規定はない」
2023年4月19日の衆議院厚生労働委員会で、加藤勝信厚生労働相は処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売(零売)について、禁止する法律上の規定はないとの見解を示しました。
加藤氏は「処方箋の交付を受けた人以外の人に対する販売・授与を禁ずる法律上の規定はない」と回答し、厚労省の「医薬品の販売制度に関する検討会」で零売のあり方を議論していることを踏まえ、「法令上の位置づけも含めて関係者から意見を聞き、検討を進めていきたい」と述べました。
10年ほど前までは、「処方箋なしでも病院の薬が買える」と看板に書いてある薬局は日本国内に数店舗しかありませんでした。しかし、ここ数年間で他の薬局との差別化を目的として「処方箋が無くても病院の薬が買える」とホームページ上に掲載している調剤薬局が散見されるようになりました。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品に関しては、やむを得ず販売を行わなければならないときに、
1.必要な受診勧奨を行ったうえで
2.必要最小限の数量を
3.販売記録を作成すれば
販売することができるというルールがあります。
しかし、販売はあくまで「やむを得ない理由がある場合」に限ります。
ということで、厚生労働省は「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」の販売に関して「不適切な表現」の一覧を開示しました。以下に示します。
不適切な表現
薬局における処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売等は、やむを得ず販売等を行わざるを得ない場合に限られており、次のような表現を用いて、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の購入を消費者等に促すことは不適切であること。
・「処方箋がなくても買える」
・「病院や診療所に行かなくても買える」
・「忙しくて時間がないため病院に行けない人へ」
・「時間の節約になる」
・「医療用医薬品をいつでも購入できる」
・「病院にかかるより値段が安くて済む」

yakkyoku
また、上記に限らず、やむを得ず販売等を行わざるを得ない場合以外でも、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を購入できるなどと誤認させる表現についても同様であること。
2022年8月5日に生労働省医薬・生活衛生局長 から「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について 」という名目で注意喚起がでましたので、各調剤薬局による”零売薬局”のアピール合戦は落ち着くのかもしれませんし、イタチごっとのように”零売”を暗に意味する”俗語”のような表現がでてくるのかもしれません。

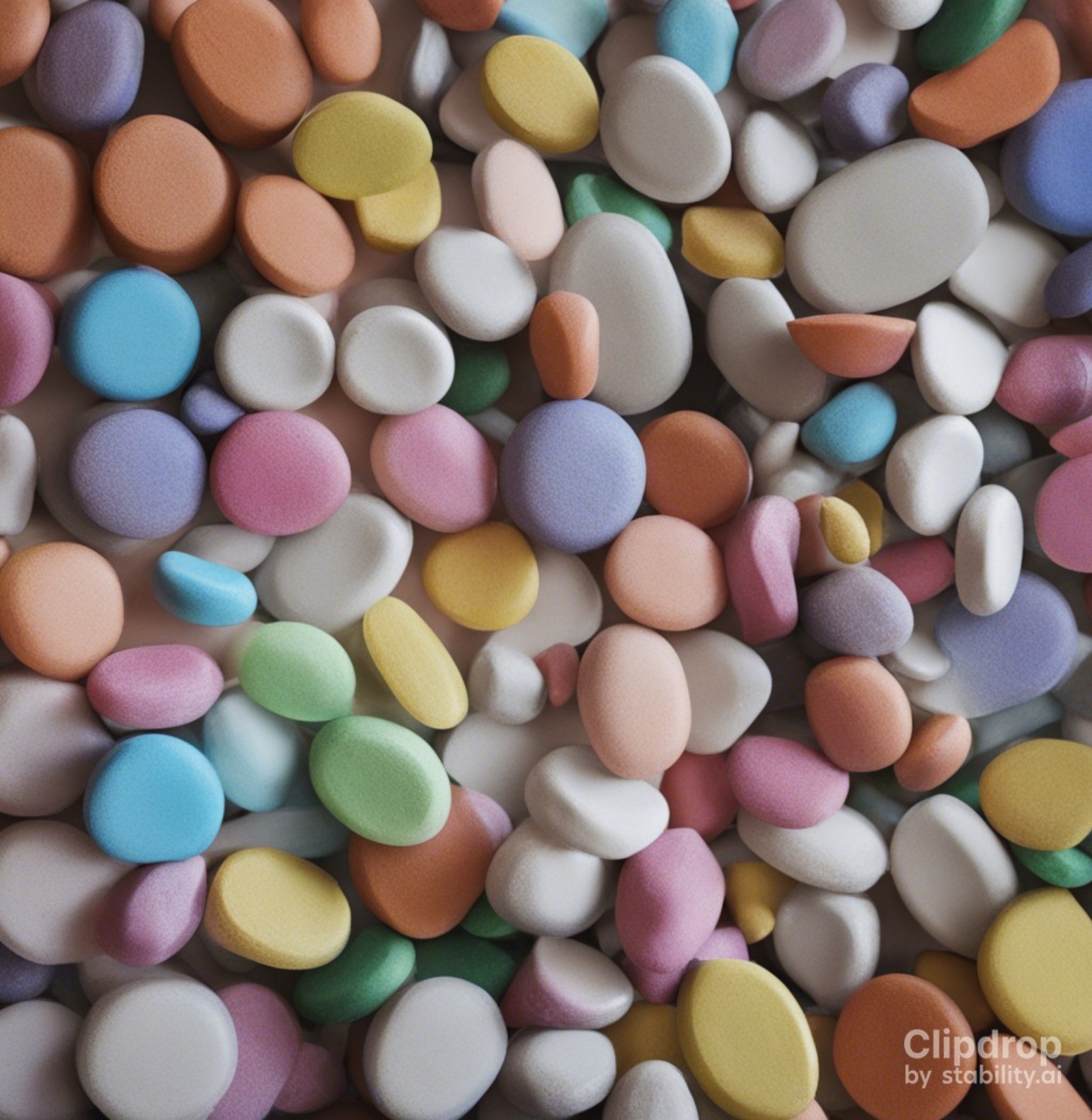
コメント