舌がヒリヒリ?口の中が変な感じ?──歯科で使われる「心の薬」のひみつ
「舌が痛い」「口の中がネバネバする」「歯に何かくっついてる気がする」──でも、歯医者さんで調べても異常が見つからない。そんな不思議な症状に悩む人がいます。
これは「舌痛症」や「口腔異常感症」と呼ばれるもので、見た目には異常がないのに、痛みや違和感を感じる病気です。実は、こうした症状には、精神科で使われる薬が歯科で使われることもあるんです。
今回は、歯科医の現場で使われることがある4つの薬について、わかりやすく紹介します。
ロフラゼプ酸エチル(商品名:メイラックスなど)
どんな薬?
ロフラゼプ酸は「抗不安薬」と呼ばれる薬で、心の緊張や不安をやわらげる働きがあります。
どう効くの?
脳には「GABA(ギャバ)」というリラックスさせる物質があります。ロフラゼプ酸はこのGABAの働きを強めて、神経の興奮をおさえてくれます。
舌痛症の人は、ストレスや不安で神経が過敏になっていることが多く、ロフラゼプ酸を使うことで「痛みの信号」が弱くなることがあります。
ここで、私たちの脳内における神経伝達について少しお伝えします。
私たちが「考える」「感じる」「動く」といったことができるのは、脳の中でたくさんの神経細胞が情報をやりとりしているからです。
そのやりとりを助けるのが「神経伝達物質(しんけいでんたつぶっしつ)」という化学物質なのですが、その中で「アクセル」のはたらきをする物質と「ブレーキ」のはたらきをする物質についてご紹介します。
グルタミン酸:脳を元気にする“アクセル
グルタミン酸は、脳の中でいちばん多く使われている「興奮性(こうふんせい)」の神経伝達物質です。
グルタミン酸の働き
• 神経細胞を活発にする
• 考える力や記憶、学習に関係している
• たくさん出ると、脳が「元気モード」になる
でも、グルタミン酸が多すぎると、神経が疲れてしまったり、興奮しすぎてしまうこともあります
GABA:脳を落ち着かせる“ブレーキ”
GABA(ギャバ)は、グルタミン酸とは反対に「抑制性(よくせいせい)」の神経伝達物質です。
GABAの働き
• 神経の興奮をおさえる
• リラックスさせる
• 不安やストレスをやわらげる
つまり、GABAは脳の「ブレーキ役」。グルタミン酸がアクセルなら、GABAはブレーキ。この2つがバランスよく働くことで、脳はちょうどよく動けるんです。
じつはグルタミン酸からGABAが作られる!
ここが面白いところ。GABA(γ-アミノ酪酸)は、もともとグルタミン酸から作られます。
変身の流れ
1. グルタミン → グルタミン酸 → GABA
2. この変化には「GAD(グルタミン酸デカルボキシラーゼ)」という酵素が必要です
3. GADがしっかり働くには「ビタミンB6」が必要となります
つまり、グルタミン酸は「元気のもと」でもあり、「落ち着きのもと」にもなるんです。
まるで、元気なヒーローが落ち着いたヒーローに変身するみたいですね。
GABAを作るのにはビタミンB6が大切です。ビタミンB6を摂取しやすい食べ物には
レバー(鳥・豚)、鳥の胸肉、大豆、にんにく、バナナ、ナッツなどが挙げられます。
________________________________________
バランスが大事!
グルタミン酸とGABAのバランスが崩れると、いろんな問題が起こることがあります。
• グルタミン酸が多すぎる → 興奮しすぎて不安やイライラ、てんかんなどの症状が出ることも
• GABAが少なすぎる → 落ち着けなくなったり、音や光に敏感になったりすることも
このバランスを保つためには、食事や睡眠、ストレスケアがとても大切です。
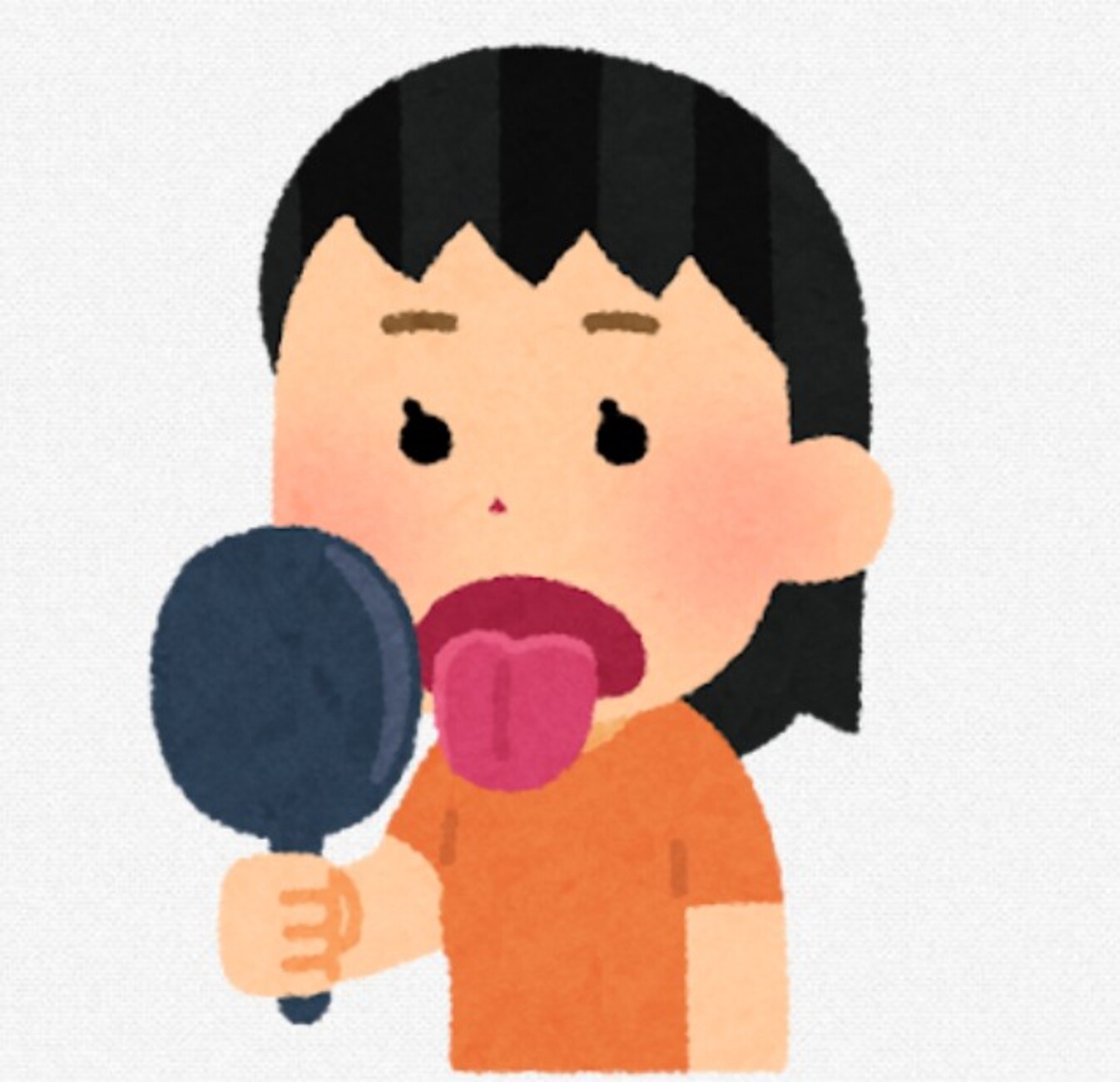
zettusyou (1)
2. セルトラリン(商品名:ジェイゾロフト)
どんな薬?
セルトラリンは「抗うつ薬」の一種で、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)と呼ばれます。気分を安定させる薬です。
どう効くの?
脳の中には「セロトニン」という“幸せホルモン”があります。セルトラリンは、このセロトニンを増やして、気分や痛みの感じ方を調整します。(正確には、脳内で作られるセロトニンの分解を抑える作用があります。効果が安定するには2週間ほど時間を要します)
舌痛症や口腔異常感症では、脳が「痛み」や「違和感」を強く感じすぎていることがあり、それをやわらげるために使われます。
ここで、セロトニンによる「痛み・違和感を抑制するはたらき」についてもう少しふかぼりしてみます。
「痛み・違和感がある」って感じるとき、実は体の中ではすごく複雑なやりとりが起きています。
でも、痛みをただ受け取るだけじゃなくて、脳には“痛みを弱める仕組み”もあるんです。
それが「下降性抑制系(かこうせいよくせいけい)」という神経伝達のシステムです。
そして、セロトニンは、この仕組みを助けることで、痛みや不安をやわらげる働きがあります。
痛みの信号はどうやって伝わるの?
まず、痛みは「ケガしたよ!」という信号が、神経を通って脳に向かって走っていくことで感じます。
この流れは「上り坂」のようなもので、体から脳へ向かうルートです。
でも、脳はただ痛みを受け取るだけじゃなくて、「ちょっと痛みを弱めよう」と逆方向に信号を送ることもできます。
これが「下降性抑制系」という神経伝達の流れです。つまり、脳から体へ向かって「痛みを抑えて!」と指令を出すルートとおもってください。
下降性抑制系ってなに?
この仕組みは、脳の中の「痛みを調整する係」が、脊髄(せきずい)という神経の通り道に向かって信号を送ります。
その信号には、セロトニンやノルアドレナリンという“脳の伝令物質”が使われます。
この伝令物質が脊髄に届くと、痛みの信号が弱くなったり、痛みの情報が途中でブロックされたりします。
つまり、痛みの音量を小さくする「脳のボリューム調整」みたいなものなんです。
セルトラリンというお薬は脳内のセロトニンというホルモンの量を安定的に保つ作用が期待されますので、結果として痛み情報の伝達を引き下げる効果が期待されます。
また、痛みだけでなく気分や不安感も改善する作用も持ちあわせますので
舌痛症や口腔異常感症のように、見た目には異常がないのに「痛い」「違和感がある」と感じる病気では、
脳の痛みの調整がうまくいっていないケースが想定されますので、セルトラリンが役立つことがあります。
ミルタザピン(商品名:レメロン、リフレックス)
どんな薬?
ミルタザピンも抗うつ薬ですが、SSRIとは違うタイプで「NaSSA(ナッサ)」と呼ばれます。気分を明るくする作用が期待されます。
どう効くの?
セロトニンとノルアドレナリンという2つの脳内物質の働きを強めて、気分や痛みの感じ方を調整します。夜眠れない人や、気分が落ち込んでいる人に使われることが多いです。
ミルタザピンには2つの作用が期待されます。
1つ目は脳内のノルアドレナリン・セロトニンというホルモンの放出を促す作用です。
(正確には、放出を抑制する受容体を遮断することで間接的に放出を促進させる作用といえます)
2つ目は、不安感の軽減です。
気分をリラックスさせる効果がある「セロトニン」というホルモンがありますが、セロトニンが過剰に脳内に放出されると
過剰な放出が「不安・幻覚」を引き起こすことが報告されています。
ミルタザピンは、セロトニンの量が増えた場合でも「不安・幻覚・嘔吐」などといった負の要素を取り除き、不安感の改善のみにセロトニンが作用できるようサポートする効果が期待されるお薬です。
舌痛症の人で、睡眠障害やうつ症状がある場合に使われることがあります。また、脳内のノルアドレナリン・セロトニンが増えますので
「下降性抑制系(かこうせいよくせいけい)」という神経伝達のシステムも活発になり、痛みが軽減する効果も期待されます。
アリピプラゾール(商品名:エビリファイ)
どんな薬?
アリピプラゾールは「抗精神病薬」と呼ばれる薬で、統合失調症やうつ病の補助薬として使われます。最近では、少量で使うことで痛みや違和感をやわらげる効果が注目されています。
これまでにご紹介した「ロフラゼプ」「セルトラリン」「ミルタザピン」とは作用が異なります。
どう効くの?
脳の中の「ドパミン」や「セロトニン」のバランスを整えることで、過剰な痛みや違和感の信号を調整します。
舌痛症や口腔異常感症で、他の薬が効きにくい場合に少量使われることがあります。
アリピプラゾールについては、ドパミンというやる気スイッチを促す脳内ホルモンの量を調整する作用がおもな働きとなります。
ドパミンが過剰に放出されすぎている場合は、それを抑え、逆に脳内のドパミン量が不足している場合は補うといった感じで
ドパミンの「調整役」のような働きがあります。
それに加えて、セロトニンの過剰分泌で起こりうる「幻覚・妄想・不安」といった負の要素を軽減する作用も期待されるお薬です。
このため、セロトニン関連で治療を勧めていても、改善が見られない場合に追加されることがあります。
ここで、アリピプラゾールはドパミンの量を調整する作用がメインとお伝えしましたが、その作用の一つ「反芻思考(はんすうしこう」の改善について詳しくご説明します。
「考えすぎちゃう…」を助ける薬、アリピプラゾールって?
1. 反芻思考ってなに?
「反芻(はんすう)思考」って、ちょっと難しい言葉なんですが、
「同じイヤなことを何度も頭の中でぐるぐる考えてしまうこと」です。
たとえば…
• 「歯の痛みや違和感、ねちゃねちゃが続いている」
• 「またなおらなかったらどうしよう」
• 「薬を飲んでいるはずなのに・・」
こんなふうに、不安を何度も思い出してしまうのが反芻思考です。
これは、気分が落ち込んだり、不安になったりする原因にもなります。
2. 反芻思考に関するアリピプラゾールの効き目は?
アリピプラゾール(商品名:エビリファイ)は、脳の中の「気分のバランス」を整える薬です。
脳の中には「ドパミン」や「セロトニン」という気分ややる気をコントロールする物質があります。
この薬は、これらの物質の働きをちょうどいいバランスに調整してくれるのです。
たとえば:
• ドパミンが多すぎる → 少し抑える
• ドパミンが少なすぎる → 少し助ける
まるで、気分のアクセルとブレーキをうまく使い分ける運転手みたいな働きです。
3. どうして反芻思考に効くの?
反芻思考は、不安や緊張が強すぎるときに起こりやすいです。
アリピプラゾールは、脳の中の「不安を感じるスイッチ」をやさしく調整してくれます。
実際に、ある患者さんでは、
このように、アリピプラゾールは、
• 不安やこだわりをやわらげる
• 気持ちの切り替えをしやすくする ことで、反芻思考を減らす手助けをしてくれるのです。
以上、歯科領域で使用されるお薬の中で「舌痛症」や「口腔異常感症」と呼ばれる「見た目には異常がないのに、痛みや違和感を感じる病気」に対して処方されるお薬の効果についてお伝えしました。
皆様の治療の一助となれば幸いです。











