「5時間以上ゲームに熱中してはダメですよ」というデータ(2023/1/7)
今回は、スイスの男性5358人(平均年齢28.26歳)を対象にして、ゲームをどの程度を行うかを調査し、5時間以上ゲームに熱中する日数が多いほど、健康を害しますよというデータが報告されたのでまとめてみます。
著者らは「ゲームに熱中すること」をbinge gamingと呼んでいます。
「binge(熱中する)」と言う言葉は、ゲームに限らずお酒の飲みすぎ(binge drinking)(通常の4~8倍)暴食(binge eating)、テレビの見過ぎ(binge watching TV)、ギャンブル依存(binge gambling)など様々な「依存症」に用いられる言葉です。
飲みすぎ・食べ過ぎ・ギャンブル依存などはいずれも健康や精神を害します。
今回はゲーム依存(熱中)(binge gaming)についての報告です。
スイスの若い男性5356人を対象として、5時間以上ゲームをプレイする頻度を調査した結果
ゲームをする頻度
毎日・ほぼ毎日:15.2%
毎週:25.5%
1週間い1回もない:33.1%
ゲームをしない:26.3%
5時間以上ゲームに熱中する頻度
毎日・ほぼ毎日:0.9%
週に何回か:1.9%
毎週:3.3%
毎月:7.4%
月に1度もない程度:7.4%
ない:40.4%
ゲームをしない:26.3%
ということで、週に1回程度、5時間以上ゲームをする割合は0.9+1.9+3.3=6.1%程度であることがわかりました。
1回に5時間以上ゲームをプレイすると、精神衛生・睡眠の質・生活満足度の低下と用量依存的に関連していることが示唆されました。
筆者らは、1回に5時間以上ゲームをプレイすることで、ゲームの仮想世界への没入感が高まり、報酬回路が過剰に刺激され、リアル世界(オフライン)の活動への関心が低下し、精神疲労を引きおこす可能性を検討しています。
また、長時間のゲームは睡眠不足と関連することが報告されており、睡眠時間だけでなく睡眠の質を低下させる可能性が示唆されています。また、この状況が長期間に及ぶと精神衛生が損なわれる可能性が検討されています。
筆者らは、上記の対策として、休息をとりながらゲームをすること、1回のゲームに費やす時間を制限することをこうさつに述べて言います。
若者がゲームに熱中しすぎることは精神的に良くないよという報告
ネットゲーム依存が疾病指定される(2018年1月)
インターネットゲームなどのやりすぎで日常生活に支障をきたす症状について世界保健機関(WHO)の国際疾病分類に「Gaming disorder(ゲーム症・障害)」として盛り込まれることになりました。
WHOによると2018年6月に公表予定となっている最新の国際疾病分類(ICD)11にて「ゲーム症・障害」が追加されるとのことです。
~ゲーム症・障害(持続又は反復するゲーム行動)~
・ゲームをする衝動が止められない
・ゲームを最優先する
・問題が起きてもゲームを続ける
・個人や家族、社会、学習、仕事などに重大な問題が生じる
などが具体的な症状としてあげられています。
アメリカにおけるインターネットゲーム障害に関する研究
診断に必要な症状の継続期間は「最低12か月」。ただ特に幼少期は進行が早いとして、すべての症状にあてはまり、重症であれば、より短期間でも依存症とみなす方針となっています。
アメリカの精神医学会では平成23年5月に「インターネットゲーム障害」に関する研究が進められており、精神疾病の一つとして提案されておりました。
インターネットで多くは複数の人が参加することがゲームを持続的に繰り返し行うことで臨床的に重大な障害あるいは苦痛が引き起こされ、12 か月の間に以下の内 5 項目あるいはそれ以上が当てはまる場合「インターネットゲーム障害」の診断基準案とされています。
1:インターネットゲームに夢中になっている。(前回のゲームのことを考えたり,次のゲームを待ち望んだりして,インターネットゲームが日常生活の主要な活動となる)
[注]この障害はギャンブル障害に含まれるインターネットギャンブルとは区別される
2:インターネットゲームが取り上げられたとき離脱症候群を起こす。(典型的な症状は,いらいら・落ち着きのなさ,不安・心苦しさ,嘆き・悲しみといったもので,薬理学的な離脱による身体症状は認められない)
3:耐性―インターネットゲームに参加する時間が増えていく必要性
4:インターネットゲームへの参加をコントロールしようとする試みが成功しない
5:インターネットゲームの結果として,インターネットゲーム以外の趣味や楽しみへの関心がなくなる
6:心理社会的な問題があると分かっていても,インターネットゲームを継続してやり過ぎてしまう
7:インターネットゲームの使用量について,家族やセラピストその他の人たちにうそをついたことがある
8:否定的な感情(無力感,罪悪感,不安など)から逃げるため,あるいはまぎらわすためにインターネットゲームを利用する
9:インターネットゲームによって,大切な人間関係,職業,教育あるいは経歴を積む機会が危うくなったり,失ったりしたことがある
厚生労働省の調査では、2012年に全国の中学生・高校生を対象とした調査によると、勉強以外に5時間以上インターネットを使用している割合は
平日で
中学生男子:8.9%
中学生女子:9.2%
高校生男子:13.8%
高校生女子:15.2%
休日では
中学生男子:13.7%
中学生女子:14.2%
高校生男子:20.5%
高校生女子:22.1%
とされており、インターネット依存が疑われる割合は
中高生男子:6.4%
中高生女子:9.9%
となっています。
2012年での調査ですので、それ以降はさらにすすんでいる可能性も考えられます。

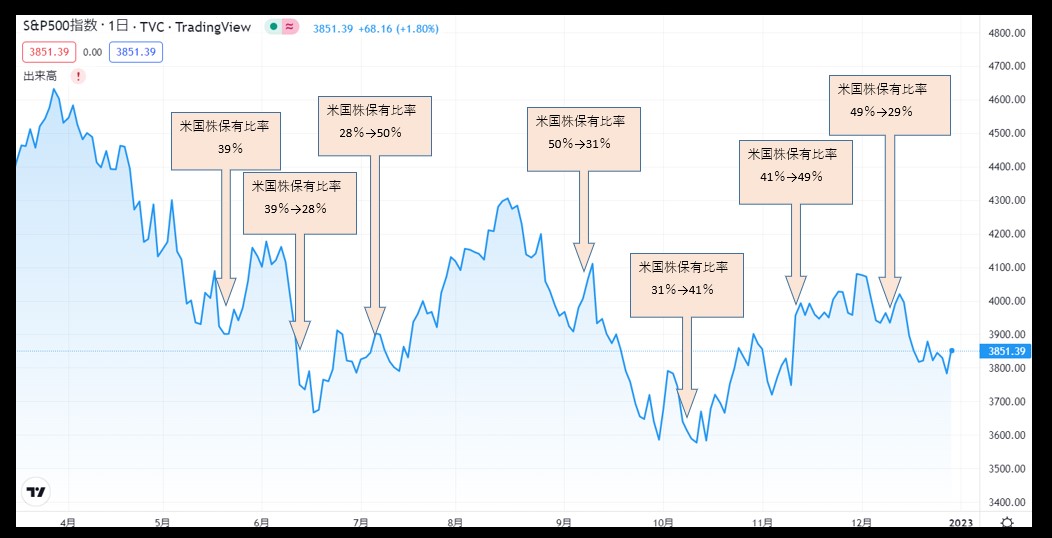

コメント