はい、承知いたしました。以下に、Barcelona大学のOriol Sibila氏らの研究内容をわかりやすく解説するブログ記事を作成しました。
気管支拡張症の治療、症状の重さがカギ?マクロライド長期療法の新たな視点
気管支拡張症と診断された方、またはそのご家族の皆様、こんにちは。今回は、気管支拡張症の治療に関する新しい研究結果をご紹介します。
気管支拡張症の治療、何が問題だったのか?
気管支拡張症は、気管支が広がり、痰が溜まりやすくなる病気です。症状がひどくなると、呼吸困難や咳、発熱などが起こり、日常生活に支障をきたすこともあります。
治療の一つとして、マクロライドという抗菌薬を長期間服用する「マクロライド長期療法」があります。しかし、抗菌薬の長期使用は、薬剤耐性を生む可能性も指摘されており、誰にこの治療を行うべきか、明確な基準が求められていました。
これまでのガイドラインでは、「年間3回以上の増悪(症状の悪化)」を経験した患者さんにマクロライド長期療法を行うことが推奨されてきました。しかし、症状が重くても増悪の回数が少ない患者さんに対しては、治療の適応が曖昧でした。
新しい研究が示す、マクロライド長期療法の新たな可能性
Barcelona大学のOriol Sibila氏らが行った大規模な研究で、この問題に対する新たな視点が示されました。
研究チームは、国際的な気管支拡張症データベース「EMBARC」に登録された1万9千人以上の患者さんのデータと、過去に行われた3つの臨床試験のデータを分析しました。その結果、症状の重さが、将来の増悪を予測する重要な要素であることが明らかになりました。
つまり、過去の増悪回数だけでなく、現在の症状が重い患者さんは、マクロライド長期療法によって症状の悪化を防げる可能性が高いということです。
研究結果のポイント
-
症状の重さと増悪リスクは密接に関連: 症状が重いほど、過去1年間の増悪回数も多かった。
-
症状の重さは増悪の独立した危険因子: 過去の増悪回数に加えて、症状の重さも増悪のリスクを高める。
-
年間3回以上の増悪経験者と同等のリスク: 過去に増悪を経験していないものの、症状が重い患者さんも、増悪のリスクは高い。
-
マクロライド長期療法の効果: 症状が重い患者さんは、マクロライド長期療法によって増悪を予防できる可能性が高い。
治療の選択肢は広がる?
この研究結果は、気管支拡張症の治療において、患者さんの症状の重さをより重視する必要があることを示唆しています。
これまでガイドラインに当てはまらない、症状が重いものの増悪回数が少ない患者さんに対しても、マクロライド長期療法を検討する価値があるかもしれません。
もちろん、マクロライド長期療法には薬剤耐性のリスクも伴います。そのため、医師とよく相談し、個々の患者さんの状況に合わせて、治療のメリットとデメリットを慎重に評価することが重要です。
まとめ
今回の研究は、気管支拡張症の治療におけるマクロライド長期療法の適応を再考するきっかけとなるでしょう。症状の重さを考慮することで、より多くの患者さんが適切な治療を受け、より良い生活を送れるようになることが期待されます。
Sibila O, et al. Lancet Respir Med. 2025 Aug 27.
抗生剤服用後の軽度な下痢が起こるタイミングについて
追記:2019年5月11日
小児における抗生物質服用後の下痢対策として使用する整腸剤の効果について
小児における抗生剤処方の際に、下痢(抗生剤関連下痢症)対策として整腸剤が処方されることをよく目にするのですが、その整腸剤の効果に関する報告がありましたので読んでみました。
小児(0〜18歳)を対象として、抗生物質使用の際に整腸剤あり群・なし群を比較して、抗生剤服用後の下痢症の発生率を調査したデータです。
結果
整腸剤高用量服用群(50億CFU以上服用群)における下痢症の発現率:13%(278/2218例)
プラセボ群における下痢症の発現率:23%(503/2207例)
ハザードリスク:0.54
報告では高用量の整腸剤を服用すると、その後の下痢症を50%程度の確率で抑えることができるという報告となっております。
ここで言う高用量の整腸剤とは1日あたり50億CFU以上の整腸剤の量を意味しているのですが、具体的な量でいいますと
ビオフェルミン配合錠には1錠あたり100万〜10億CFUの善玉菌が含まれているますので
ビオフェルミンR錠剤 1回2錠、1日3回といった用法であればギリギリ50億CFUを満たすか満たさないかというレベルの量です。
レベニン散には1gあたり最大で18億CFUの善玉菌が含まれている可能性がありますので(概算です)
レベニン散を1回1g、1日3回といった用法であれば50億CFUを満たすのでは?といったレベルの量です。
ちなみに整腸剤低用量(50億CFU以下)でもプラセボと比べると下痢症の発現率は低いデータが示されていますので、抗生剤と整腸剤はセットで飲むと下痢を起こす頻度が半分ほどに低下するというイメージをもっていいかと思います。
小児科では親御さんにお薬の内容をお伝えすることが多いのですが、具体的なデータを完結にお伝えすることは親御さんの安心にもつながると思います。例えばですが抗生剤と一緒に処方される整腸剤について、詳しく知りたい親御さんがおりましたら、
「整腸剤と抗生剤を一緒に飲むと、うんちがゆるくなりにくくなります。整腸剤を飲む・飲まないで比べると下痢を起こす頻度は倍くらい差があるというデータも報告されております」
といったコメントも有益な情報となるのかもしれません。
以下は2018年12月8日に記載しました抗生剤服用後の下痢が起こるタイミングについての内容です。
先日、抗生剤を飲んだ患者様から以下の連絡を受けました。
「抗生剤を夜に飲んで寝ました(抗生剤の服用を開始した)。翌日朝から水のような下痢がでました。お薬の説明書きを確認したところ“下痢になった場合は病院・薬局にご連絡ください”と書いてあったので連絡したよ」
抗生剤を飲むと腸内の細菌数が減る、または細菌のバランスが崩れることで腸内環境に変化が起こって下痢になることは多くの薬の教科書に記されております。しかし抗生剤を服用してから、どれくらいの期間で下痢が起こりうるかについては記されておりませんでした。そこで今回は抗生剤服用から軽度の下痢が生じるまでに期間についてしらべてみました。
結論
・腸内環境の変化によって下痢が生じるタイミングは人それぞれなのですが、抗生剤服用開始から2〜3日後に軽度の下痢が生じる報告が多い(だいたい50%程度でしょうか)ことを、抗生剤を販売している製薬会社の学術へ確認しました
整腸剤に含まれる善玉菌は、服用を中止した後も腸の中に定着する?
風邪で下痢になるかどうかについて
いわゆる風邪は空気の通り道にウイルスが感染することで生じる気道の感染症ですので、おなかが緩くなるケース(下痢・吐き気)は少ない印象です。
初期症状としては、喉の痛み・発熱・関節痛・悪寒など
整腸剤の効果・使用方法・違いについて(ビオフェルミン・乳酸菌・糖化菌・酪酸菌)
感染性胃腸炎は消化管にバイキン(ウイルスや細菌など)が入って悪さをする疾患です。この場合は、お腹が緩くなるケース(下痢・吐き気)が生じます。
初期症状としては、腹痛・下痢・嘔吐・発熱・関節痛などです。
風邪でも感染性胃腸炎でも「発熱・関節痛」といった症状が共通するため、本当の初期症状での判別が難しい場合もあります。
感染性腸炎治療薬ダフクリア錠(フィダキソマイシン)200mgについて
整腸剤に含まれる善玉菌は、服用を中止した後も腸の中に定着する?
抗生剤服用での下痢について
クラリス・メイアクト・フロモックスを製造販売している製薬メーカーへ抗生剤服用後に軽度の下痢が生じるまでの時間・日数を確認してみました。回答は「腸内環境によって日数はさまざまですが、報告データ上では2〜3日目に軽度の下痢が生じる割合が50%程度でしょうか」という感じでした。クラリスを販売しているメーカーからの回答では初日に下痢が生じる割合は5%(だいたい)ほどだそうです。
熱がでたので病院を受診し、抗生剤が処方された場合、この時点では「風邪」または「感染性胃腸炎」のどちらの可能性も秘めている状態といえます。
抗生剤を服用して2〜3日経過後に便が緩くなるのであれば、抗生剤服用による「軽度の下痢」という可能性は一つの選択肢として想定されるかもしれません。
抗生剤の服用を開始して(1回飲んで)10時間後に水のような下痢が出た(今回ワタシが電話連絡をいただいた事例)。この場合、可能性として抗生剤による下痢という可能性よりは、他の原因があるような気もします。(例えば吐き気を伴うかどうかなどの症状が気になるところです)
プロテバイオティクスヨーグルトには抗生剤による下痢を予防する効果はない
私のイメージですが、抗生剤の服用を開始すると、腸管内の腸内細菌(善玉菌・悪玉菌・日和見菌)に対して抗生剤が作用して生菌数が減っていきます。連日服用を続けることで菌の減少数が大きくなっていき、どこかのタイミングで軟便・下痢となることがあります。ざっくりとしたデータしかないものの、抗生剤服用開始から軟便・下痢となるタイミングが2〜3日目以降になることが多いようです。
少し話はそれますが、成人の抗生剤服用に伴う下痢の予防として普通のヨーグルトを摂取した場合と、La-5アシドフィルス菌、ビフィズス菌Bb-12といった善玉菌を多く含むプロテオバイオティクスヨーグルトを摂取した場合を比較したデータによると、下痢を発症する割合はどちらも同程度であることが報告されています。
まとめ
抗生剤を飲んだあとに軽度の下痢が発症するまで日数は、個人の腸内細菌環境に依存するものの、2〜3日後に生じることが比較的多いようです。
抗生剤を飲んだ直後に下痢になるケースはゼロではないものの、頻度は低い
善玉菌を豊富に含んだヨーグルトに、抗生剤関連の下痢を予防する効果はないという報告がある
整腸剤の効果・使用方法・違いについて(ビオフェルミン・乳酸菌・糖化菌・酪酸菌)
注意)高齢者や入院患者さんが抗生物質を使用した際に、ある種の悪玉菌が異常に増殖して生じる“偽膜性大腸炎”と今回テーマ“軽度の下痢”とは異なりますのでご了承ください
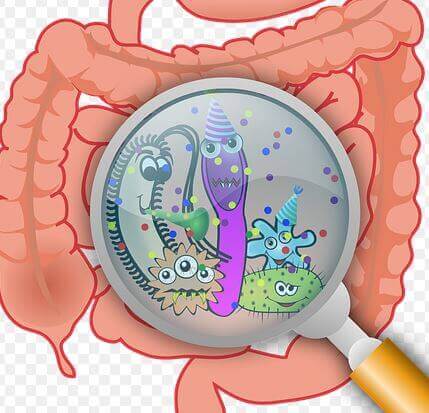



コメント