アライ(ALLI)の代わりに摂りすぎた脂質を排泄させるためには?
腹部の太めの方を対象として販売が開始された医薬品としてALLI(アライ)があります。
アライの服用対象となる方は腹囲が男性で85㎝以上、女性で90㎝以上となっており、購入するために敷居があるんですよね。
アライを飲むまでではないものの、お腹周りが気になる方に「食事療法」が大切となりますが、食事療法とは「食べ過ぎないこと」が前提となります。
頭ではわかっているものの、そこは人ですから「食べ過ぎないこと」を繰り返すとストレスがたまるものです、そのため「食べ過ぎたあと」にできることを考えるのがいいかなぁと思うんですね。
そこで、今回はアライ(ALLI)の効き目(作用)をお話しした後で、同じような作用とまではいきませんが、毎日の食事で何かできることは無いかについてお話を進めていきます。
アライってどんな薬?
アライは、食べすぎた油(脂肪)を体に吸収されないようにする薬です。食事のときに飲むことで、体に入る脂肪の量を減らして、太りにくくすることができます。
どうやって働くの?
食べ物に含まれる脂肪は、体の中で「リパーゼ」という酵素によって分解されて、小さくなってから吸収されます。
でも、アライには「オルリスタット」という成分が入っていて、このリパーゼの働きを止めてしまうんです。
その結果食べた脂肪のうち、約25%は分解されず、吸収されずにそのままうんちとして出ていくんです
つまり、アライは「脂肪をブロックして外に出す薬」なんですね。
といことで、腸管内におけて、脂質がどのような流れで体の中に吸収されるかをしることができれば、「食べ過ぎで太る」まで経路がイメージしやすかと思います。
油っぽい食事が腸管内に到達すると、膵臓から分泌されるリパーゼによって分解を受けた後、細かい油は胆汁酸によって水に溶けやすい状態(ミセル)となり、水の中でもお安定した状態となり腸管の粘膜から体の中で吸収されていきます。
アライ(ALLI)がリパーゼを阻害するわけですが、毎日食べる食事の中で「胆汁酸」の働きを軽度に阻害できれば体に吸収される油分の量を減らすことができますよね。この役割を担うのが食物繊維です。
食物繊維には、胆汁酸を吸着して排泄を促す作用があります。
食物繊維と胆汁酸の関係
胆汁酸の再吸収阻害: 胆汁酸は、肝臓で作られた後、胆嚢に貯蔵され、食事の際に十二指腸に分泌されます。十二指腸で脂質の消化を助けた後、通常は腸の末端で再吸収され、肝臓に戻って再利用されます(腸肝循環)。しかし、食物繊維は、腸管内で胆汁酸と結合し、再吸収を阻害します。
胆汁酸の排泄促進: 食物繊維に結合した胆汁酸は、便として排泄されます。これにより、腸管に留まる胆汁酸の量がへるとともに、体内の胆汁酸の量が減少し、肝臓はより多くの胆汁酸を新たに生成する必要があります。
コレステロールの低下: 胆汁酸はコレステロールから作られるため、胆汁酸の排泄が増えると、肝臓はコレステロールを消費して新たな胆汁酸を生成します。この結果、血中のコレステロール値が低下する可能性があります。
特に効果的な食物繊維
水溶性食物繊維: ペクチン(リンゴ、柑橘類などに含まれる)、β-グルカン(オーツ麦、大麦などに含まれる)などの水溶性食物繊維は、胆汁酸との結合力が強く、排泄を促す効果が高いとされています。
不溶性食物繊維: セルロース(野菜、穀物などに含まれる)、リグニン(木質植物などに含まれる)などの不溶性食物繊維も、腸内環境を整え、胆汁酸の排泄を間接的に助ける効果があります。
注意点
食物繊維の過剰摂取は、お腹の張りや便秘を引き起こす可能性があります。
食物繊維を十分に摂取するためには、水分も十分に摂るようにしましょう。
ということで、野菜を食べることの意義は、
食べ過ぎたコレステロールの排泄を促す+コレステロールの吸収を少しおさえる
という2つの側面を持つと認識して捉えることが、コレステロールの管理に有益であると私は考えます。
日本人の痩せている高齢者・糖尿病の高齢者で認知症リスクが高い
日本老年学的評価研究のデータによると、日本の高齢者では痩せている方と糖尿病の方で認知症発症リスクが高いことが報告されました。
痩せている方・糖尿病の方は認知症リスクが高い
被験者:3696人(平均年齢:73.4歳)
調査期間:5.8年間(平均)
結果
被験者3696人のうち338人(9.1%)が認知症を発症しました。
認知症を発症した方の中で、いわゆる生活習慣病にかかっていない標準体重の方を基準としたときに、体重の増減・疾患の有無でどれほど認知症の発症リスクが高くなるかというデータを確認した結果
男性
糖尿病にかかっていると認知症発症リスクが2.22倍
痩せていて(BMIが18.5kg/㎡未満)脂質異常症(コレステロールが高い)の場合、認知症発症リスクが4.15倍
女性
糖尿病にかかっていると認知症発症リスクが2倍
痩せている(BMIが18.5kg/㎡未満)と認知症発症リスクが1.72倍
痩せていて(BMIが18.5kg/㎡未満)高血圧症の場合、認知症発症リスクが3.79倍
また、総合的な統計としては痩せていて血圧が高い高齢者、痩せていて脂質異常症の高齢者において認知症発症リスクが高いという結果となっています。
高齢者の平均身長・平均体重
総務省統計局のまとめによると
70歳以上の男性の平均身長は162.1㎝、体重61.4kgであり、BMIは23.37
(BMI:23.37は、18.5~25の間に入っているので普通体重です)
70以上の女性の平均身長は148.2cm、体重50.3kgでありBMIは22.9
(BMI:22.9は、18.5~25の間に入っているので普通体重です)
というデータがあります。
今回の認知症発症リスクで言われている「痩せている」という定義はBMIが18.5未満を指標としています。概算ではありますが、70歳以上の方の平均身長における「痩せている」体重を試算したところ
男性:身長:162.1cm、体重48.5kg(BMI:18.46)
女性:身長:148.2cm、体重40.5kg(BMI:18.44)
上記のような身長体重の方は、パッと見で「痩せている」と気づくことができるように思われます。痩せており、高血圧・脂質異常症にかかっている方が身の回りにおられましたら、認知症発症リスクについて注意喚起を行っても良いかもしれません。
今回の報告は日本国内における認知症発症リスクについてのものですが、海外でも同様の報告がなされており、BMIが高めですと認知症発症リスクが0.9倍になるのに対して、BMIが低い場合は認知症発症リスクが2.5倍まで上昇するという報告がなされておりますので、定期的な体重測定は認知症リスク管理として有益なのかもしれません。
体重減少と認知症発症リスク増加に関する具体的な研究はわかりませんが、運動量の低下、食事摂取量の低下(特にタンパク質摂取量の低下)といったことが要因かもしれません。
卵が先か鶏が先かの議論になるようですが、
・認知機能が低下→動量が低下→食事摂取量も低下→体重が減少した
・運動量低下→食事摂摂取量の低下→体重が減少した→認知機能が低下した
上記のどちら進行経緯となるのかはわかりませんし、もしかしたら加齢に伴い運動量低下・認知機能低下が同時に起こるのかもしれません。いずれにしても本人だけでなく、その家族や医療スタッフは外観変化・体重変化を定期的に確認する意義はあるかと思います。
痩せていること、糖尿病は認知症発症リスクを増加させる(日本人対象データ)
以下は2019年6月19日に記載しました内容です
認知症施策大綱(案)が作成され、医療に従事する薬剤師6万人はる認知症対応力向上研修を受講
2019年6月19日、認知症施策推進大綱がまとめられました。団塊の世代が75歳以上となる2025年(令和7年)に向けて認知症に対する対策として
「認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進する」ことを示しました。認知症施策推進大綱(全55ページ)に記されている内容のうち、薬剤師関連の業務を確認してみました。
早期発見・早期対応、医療体制の整備
かかりつけ医や地域包括支援センター等が認知症の早期発見・早期対応における役割が期待されております。地域包括支援センターとは地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関であり、各市町村に設置されております。地域包括支援センターには保健師・ケアマネージャー・社会福祉士が配属され専門性を生かして相互連携しながら業務が行われております。
かかりつけ機能に加えて地域の医療機関、認知症疾患医療センター、地域包括支援センター等との日常的な連携機能を有する歯科医療機関や薬局等も、認知症の早期 発見・早期対応における役割が期待される。
これらの専門職が高齢者等と接する中で、 認知症の疑いがある人に早期に気付き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、 その後も認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理、服薬指導、本人や家族への支援等 を適切に行うことを推進する。
かかりつけ薬剤師・薬局による継続的な薬学管理と患者支援を推進するとともに、かかりつけ医等と協働して高齢者のポリファーマシー対策をはじめとした薬物療法の適正化のための取組を推進する。

医療従事者等の認知症対応力向上の促進
○認知症の早期発見・早期対応、医療の提供等のための地域のネットワークの中で重要な役割を担う、かかりつけ医、歯科医師、薬剤師、看護師等に対する認知症対応力向上研修、かかりつけ医を適切に支援する認知症サポート医養成のための研修を実施する。
医療従事者に対する認知症対応力向上研修受講者数
・薬剤師:6万人(2018年3月時点では1万7000人が受講しております)
医療に従事する薬剤師は約25万人ほどおりますので、1/4ほどの薬剤師が受講することが求められております。
かかりつけ薬剤師としての役割を発揮できる薬剤師を配置している薬局数:70%
薬剤師関連の記載内容としては「認知症対応力向上研修を受講する人数」を増やすことと、かかりつけ薬剤師を配置している薬局数を増やすことといった感じでしょうか。
薬剤師認知症対応力向上研修とは
高齢者が受診した際や受診後等に接する薬局・薬剤師に対し、認知症の人本人とその家族を支えるために必要な基本知識や、医療と介護の連携の重要性等を習得するための研修を、各都道府県薬剤師会が開催しております。
受講カリキュラムが開催する都道府県薬剤師会によって異なるのですが、だいたい3時間半~4時間の講義(無料)を受けて修了証が手渡されることになります(研修単位2単位)
合同会社 HAM 人・社会研究所のホームページには薬剤師認知症対応力向上研修に関する教材が公開されておりました(H31年2月25日誤字修正済み)
薬剤師認知症対応力向上研修テキストは全96ページからなる教材であり、薬剤師が高齢化社会における認知症とどのようにかかわっていくかが記されています。
薬剤師認知症対応力向上教材の概要
・認知症の病態を知ること
・認知症の疑いがある患者さんに気づき、かかりつけ医や関係機関等と連携して対応すること
・認知機能が低下している方に対して、薬学管理・服薬指導を適切に行い、薬物治療が赤核に行われるよう支援すること
今後、かかりつけ薬剤師を満たすための要件や調剤報酬関連の要件に「薬剤師認知症対応力向上研修」が加わるかどうかは不明ですが、患者様と接する現場で求められる知識となっていくかと思われます。

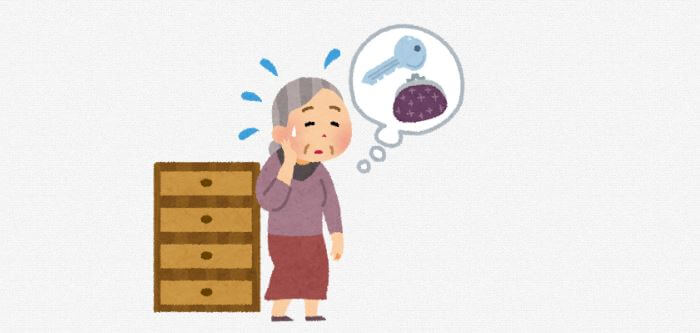


コメント