- アルツハイマー病の疑いを簡単な質問で判別する方法(2024/11/24)
- リリーのケサンラ点滴静注(ドナネマブ)が国内で新薬に承認(2024/9/25)
- 認知症の生命予後は?(2024/8/25)
- 米国食品医薬品局(FDA)、イーライリリー社の早期アルツハイマー病治療薬Kisunlaを承認
- 米国食品医薬品局(FDA)によるアルツハイマー病の治療薬分類(2024/1/9)
- アルツハイマー型認知症治療薬「レケンビ点滴静注500mg/5ml」の薬価は11万4443円(2023/12/13)
- 犬を飼育する高齢者は認知症リスクが4割減少
- アルツハイマー病を治療する超音波発信機ヘッドセットの治験開始(2023/11/17)
- アルツハイマー病のリスクを3.5倍に高める遺伝子のメカニズムを解明
- 認知症治療薬「ドナネマブ」は投与1年で半数が治療を終了できる(2023/10/11)
- レケンビ点滴の働きをお伝えする動画を作成しました(2023/10/1)
- アルツハイマー病進行抑制薬「ドナネマブ」をイーライリリーが厚生労働省へ承認申請(2023/9/28)
- アルツハイマー病進行抑制薬「レケンビ点滴静注用200mg/500mg」(成分名:レカネマブ)が承認されました(2023/9/26)
- アルツハイマー病進行抑制薬「レケンビ点滴静注用200mg/500mg」(成分名:レカネマブ)の承認を審議(2023/8/8)
- アルツハイマー病進行抑制薬「ドナネマブ」の治験データ(2023/8/6)
- 米国でアルツハイマー治療薬「レカネマブ」を投与するとタウタンパクの蓄積を遅延させる(2023/7/21)
- 米国でアルツハイマー治療薬「レカネマブ」をFDAが正式に承認(2023/7/16)
- アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」をエーザイが厚生労働省の優先審査品目に指定されました(2023/1/31)
- アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」をエーザイが日本国内で承認申請しました。(2023/1/17)
- アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」が米国FDAに承認されました。(2023/1/7)
- アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」投与後の脳出血死亡例について(2023/1/3)
- アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」は症状悪化の抑制効果あり(2022/12/2)
- アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の効果について(2022/10/1)
- アルツハイマー病の原因が解明か?脳内に咲く「毒の花」に不要蛋白質が蓄積(2022/6/12)
- 生活習慣病とアルツハイマー型認知症の発症リスクについて
- ドネペジル経皮吸収型製剤を「興和」がライセンス契約、製造販売承認申請(2022/4/22)
- お昼寝の時間&回数とアルツハイマー型認知症の進行には双方向の関係がある
- 頭痛と認知症の関係について
- アルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」の効果について
- エーザイ「早期アルツハイマー病治療薬”レカネマブ”」を米国FDAへ段階的申請プロセス開始(2021/9/29)
- アルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」が米国で承認される(2021/6/8)
- アルツハイマー病治療薬“アデュカヌマブ”を米国FDAが受理(2020/8/20)
- アルツハイマー病治療薬“アデュカヌマブ”を米国FDAへ申請(2020/7/8)
- アルツハイマー病治療薬“アデュカヌマブ”が医薬品となりうるか?(2019/12/12)
- エーザイが早期アルツハイマー予防薬”BAN2401”の国内臨床治験開始(2021/1/24)
アルツハイマー病の疑いを簡単な質問で判別する方法(2024/11/24)
慶応大学の研究チームは「簡単な質問」でアルツハイマー病の疑いを判別する方法を提案しています。
アルツハイマー患者と健康な人合わせて155人に以下の簡単な質問をなげかけて、その答えや振る舞いから病気を見分けられないか実験を行いました。
質問は、以下の内容です。
・現在、こまっていることがあるか?
・3カ月以内で気になるニュースがあるか?
・現在、楽しみはあるか?
という3つです。
現在、困っていることがあるか?と3カ月以内で気になるニュースがあるか?という2つの質問に対して、いずれも「無い」と回答し、3番目の「現在、たのしみはあるか?」という質問に具体的に回答した人の83%がアルツハイマー病の精密検査で陽性だったということです。
さらに、「最近、家族で旅行したことはありますか?」などの質問に対して、質問に自分で答えられず、付き添い家族らに助けを求めて振り返る動作をした人の87%がアルツハイマー病の検査で陽性だったとまとめています。
研究者らは、質問への答えや振る舞いを見れば、病気のの疑いをある程度見分けられるとしています。
リリーのケサンラ点滴静注(ドナネマブ)が国内で新薬に承認(2024/9/25)
日本イーライリリーはケサンラ点滴静注液350ml(ドナネマブ)が「アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制」を効能・効果とする新薬として承認されたことを公開しました。
今後の予定としては薬価の審議をへて、2024年11月にも保険適用となる見通しです。
ケサンラ点滴静注は、脳内に沈着したアミロイドプラークを特異的に標的とし、プラークの除去をもたらす作用が期待され、りアルツハイマー病(AD)による認知機能や日常生活機能の悪化の遅延をもたらすことが期待される製剤です。
ケサンラの用法・用量は、通常、成人にはドナネマブ(遺伝子組換え)として1回700mgを4週間隔で3回、その後は1回1400mgを4週間隔で、少なくとも30分かけて点滴静注するというものです。
ケサンラの特徴としては、投与期間が減速8カ月までと制限されていることで、脳内のアミロイドプラークの除去が確認された段階で、投与が完了されるという特徴があります。投与開始から12カ月時点でアミロイドPET検査を行い、アミロイドプラークの除去の確認を求めています。
先に発売されたエーザイの類似薬、レケンビは3年間の臨床データが公開されており、長期投与が前提のようですが、リリーから発売されるケサンラは投与日数に制限があることが特徴です。
認知症の生命予後は?(2024/8/25)
認知症性疾患全体の生命予後のメタアナリシスによれば、認知症全体としての死亡率は、認知症のない者に比べて5.9倍も高いと報告されています。
認知症全体の平均では、発症年齢が68.1±7.0歳で、診断された年齢は72.7±5.9歳。そして、初発から死亡まで7.3±2.3年で、診断から死亡まで4.8±2.0年と言われています。
ADでは、初発から死亡まで7.6±2.1年、診断から死亡までが5.8±2.0年とされる。注目すべきは、いわゆる4大認知症性疾患の中で、ADの生命予後が一番良いことです。
ADの診断がついた患者さんやその家族から、余命は何年か?の質問を筆者が受けたなら、以上のメタアナリシスの結果を参考にして4~8年程度という回答が一般的のようです
米国食品医薬品局(FDA)、イーライリリー社の早期アルツハイマー病治療薬Kisunlaを承認
2024年7月2日、米国食品医薬品局(FDA)は、イーライリリー社の早期アルツハイマー病(AD)治療薬Kisunla™(350mg/20mL)を軽度認知障害(MCI)または軽度認知症の段階でアミロイドβ病理を示唆する所見が確認された成人患者に適応として承認しました。
Kisunla(ドナネマブ)が早期アルツハイマー病の治療薬としてFDAが承認
Kisunlaの特長
- 毎月1回点滴静注により投与
- アミロイドプラークが除去された時点で投与を完了できるアミロイドプラークを標的とした治療薬
- 臨床試験では、Kisunla投与群はプラセボ群と比較して、記憶、思考、日常の機能を統合的に測定するアルツハイマー病評価尺度(iADRS)において35%の有意な進行抑制を示しました。
- Kisunla投与群はiADRSが22%低下し、統計学的に有意でした。
- Kisunlaは、アミロイド関連画像異常(ARIA)などの副作用を引き起こす可能性があります。
専門家のコメント
- Alzheimer’s Drug Discovery Foundation の共同設立者兼最高科学責任者であるHoward Fillit医学博士は、「今回の承認は、ADの標準治療の進化に向けた新たな一歩であり、ADコミュニティーが待ち望んでいた希望です。」と述べています。
米国食品医薬品局(FDA)によるアルツハイマー病の治療薬分類(2024/1/9)
FDAによるアルツハイマー病治療薬の分類に関する要約が報告されていましたので下記します。
認知症の症状を緩和する薬剤としては、認知機能の低下を緩和する薬剤、認知症の行動や心理症状を緩和する薬剤に分類できます。
・心理症状を緩和する薬剤としてレキサルティ、睡眠障害の治療薬としてベルソムラが該当します。
・認知症の症状を緩和する薬剤としては
ドネペジル:アセチルコリンレベルを増加させ、希突起膠細胞の分化を促進し、アミロイドβ毒性保護作用を示します。心臓伝導系の副作用が報告されています。
リバスチグミン:1日1回の貼り薬。ドネペジルよりも心臓に対する副作用リスクは低いものの、貼付部位のかゆみが問題となります。
ガランタミン:短期間で認知症の症状を改善する作用に加えて、心理症状の発症を遅延させる報告もあります。また複数の代謝経路を有するため、薬物相互作用が生じにくいという特徴があります。ドネペジル同様に心臓伝導系の副作用には注意が必要です。
メマンチン:神経保護の改善に加えて、抗パーキンソン病薬や抗うつ薬としても作用することが期待されています。
レケンビ点滴静注:アミロイドβの負担を軽減します。脳内のアミロイドβプラークの源線維構造と結合して、除去します。ApoE4遺伝子を有する被験者にはアミロイド関連画像異常を引き起こすリスクがあります。
米国食品医薬品局(FDA)のアルツハイマー病に関するガイドラインまとめ
アルツハイマー型認知症治療薬「レケンビ点滴静注500mg/5ml」の薬価は11万4443円(2023/12/13)
2023年12月13日、アルツハイマー病治療薬「レケンビ点滴静注」の薬価収載が了承されました。
レケンビ点滴静注200mg/2ml(1瓶):4万5777円
レケンビ点滴静注200mg/2ml(1瓶):11万4443円
体重50kgの人に500mg製剤を使用した場合の年間1人当たりの薬剤費は298万円と試算されます。
保険上の留意事項も発出され、初回から18カ月を超える連続投与については、継続が必要と判断される理由をレセプトに明記することが求められました。
また、中等度以降のアルツハイマー病による認知症と診断された患者さんに対しては、有効性が確立されていないため、投与継続を行う場合には、再評価を行い、認知機能の低下および臨床症状の重症度範囲を示し、継続が必要と判断される理由をレセプトに明記することが求めらえれます。
使用する患者要件としては、認知機能の低下及び臨床症状の重症度範囲を満たすほか、MRI検査の実施が可能であることが求められます。また、アミロイドPETまたは脳脊髄液(CSF)検査を実施し、アミロイドβ病理を示唆する所見が確認されることが求められます。
日本人のアルツハイマー病患者さんを対象としたメマリー錠の効果について
中等度から重度のアルツハイマー病患者(日本人)を対象としたメマリー錠の有用性について報告がありました。(Expert opinion on pharmacotherapy/2018年3月6日)
対象:中等度~重度のアルツハイマー型認知症患者633名
メマリー20mg/日服用群:318例
プラセボ服用群:315例
中等度から重度のアルツハイマー患者さん(日本人)を対象としたメマリー錠の効果について
上記のの割合でランダムに振り分けて24週間(約半年)服用した時の臨床試験結果を報告しています。
評価項目
SIB-J:認知症変化印象尺度
認知機能を評価するための検査であり、社会的相互行為、記憶、見当識、注意、実行、視空間能力、言語、構成、名前への志向の9項目から構成されています。患者との面接により評価を行います。得点の範囲は100~0点(正常→重度)となっています。
若年性認知症を対象としたメマリーとレミニールの効果に関する症例
CIBIC plus:患者および介護者との面接により全般的な臨床症状の変化を評価するための検査です。状態のあらまし、認知機能、行動、日常生活動作能力の4領域の患者の状態を、「1.大幅な改善」→「7.大幅な悪化」及び「判定不能」で評価します。
BEHAVE-AD:介護者等の情報をもとに認知症における行動・心理症状を評価するものです。情報をもとに7つの解釈度25項目について0~3まで4段階で重症度を評価します。
結果
メマリー20mg/日服用群とプラセボ服用群を比較して、認知機能悪化の減少をオッズ比で評価しています。
SIB-Jのオッズ比:0.52
CICIC plusのオッズ比:0.53
BEHAVE-ADのオッズ比:0.53
いずれも有意差をもってメマリー服用群が50%程度の認知機能悪化減少を示しています。
筆者らは「メマリーを服用することは、でアルツハイマー型認知症の認知機能改善だけでなく、行動・心理症状を改善する治療選択肢となりうる」とまとめています。
犬を飼育する高齢者は認知症リスクが4割減少
東京都健康長寿医療センターの調査によると犬を飼育する高齢者では認知症の発症リスクが4割減少するデータが公開されました。
被験者:東京在住の1万1194人(平均年齢74.2歳)
被験者のうち犬の飼育率は8.6%、猫の飼育率は6.3%でした。
データの採取法は、2020年までの介護保険情報に基づく要介護認知症の新規発症率が5%であり、犬の飼育者、猫の飼育舎それぞれの認知症発症リスクを評価委しています。
その結果、犬を飼育していない群と比較して、犬を飼育している群では認知症の発症リスクが0.6(4割減少)でした。
猫を飼育していない群と比較して、猫を飼育している群の認知症発症リスクは0.98(ほぼ変わらない)というデータでした。
この要因として、犬を飼っている人では運動習慣があること、社会的に孤立していないことが要因として挙げられました。
犬を飼っておらず、運動習慣がない人の認知症発症リスクを1とした場合、犬を飼っていて定期的な運動習慣がある人の認知症発症リスクは0.37(63%減)、犬を飼っていて社会的に孤立していないひとでは認知症発症リスクが0.41(59%減)と、いずれも認知症の発症リスクが低い傾向にありました。
アルツハイマー病を治療する超音波発信機ヘッドセットの治験開始(2023/11/17)
東北大のベンチャー企業「Sound Wave Innovation」は脳に超音波を上げることでアルツハイマー病の進行を抑制する臨床試験を開始したことを公開しました。
創業者の川下宏明らのチームは、脳内の血管内皮細胞が振動刺激をうけると、酵素が活性化することに着目し、マウスの脳に超音波を当てる検証でアミロイドβタンパクの蓄積が抑制されることや、血管が再生することを確認し、ヒトへの応用を模索していました。
Sound Wave Innovation社が開発した器具はヘッドセットのように頭(こめかみ)に取り付ける超音波発信器です。
2018年から少人数の治験が実施されており、安全性と一定の有効性が確認されていました。今回は全国17の医療機関にて220の被験者を募集しています。被験対象者は軽度認知障害または軽度アルツハイマー患者としています。
同社は2028年の実用化を目指すとしています。
Sound Wave Innovation社がアルツハイマー病治療用の超音波発信器の治験を開始
アルツハイマー病のリスクを3.5倍に高める遺伝子のメカニズムを解明
慶応大学の研究チームはアルツハイマー病のリスクを3.5倍に高めると言われている遺伝子「APOE4」のメカニズムを解明したことを「ステムセル・リポーツ」で発表しました。
報告では、人工的にAPOE4遺伝子を組み込んだiPS細胞を神経細胞と一緒に培養すると、一般細胞と比較して、神経細胞表面からの情報伝達作業を担う「スパイン」という突起の長さが20%短くなっていたことが記されています。
筆者らは、APOE4遺伝子をもつ患者の脳内では、細胞外マトリックスEDIL3が増加し、神経細胞のスパイン構造を変化させることで症状を進行させることが示唆しています。
認知症治療薬「ドナネマブ」は投与1年で半数が治療を終了できる(2023/10/11)
米国イーライリリーは会見で「開発中のアルツハイマー病治療薬「ドナネマブ」は投与開始から1年間の時点で、約半数の患者のアミロイドプラークを除去でき、治療をとめることができる」と述べました。
早期アルツハイマー型認知症の患者のうち半数以上の患者でアミロイドプラークの除去を12カ月以内に達成したとしています。また、18カ月間投与すれば、ほとんどの患者でアミロイドプラークの除去ができることも報告しています。
臨床第三相試験の結果、ドナネマブ投与群はプラセボ群と比して、日常生活の機能低下を40%抑えることができ、投与してから1年経過時点でドナネマブ投与群の47%で症状の進行を認めなかったとしています。
アミロイドプラークに関しては、除去した後も再びゆっくりと沈着を始めることが予測されており、再沈着が起きた場合に再び投与することについて検証するとしています。
レケンビ点滴の働きをお伝えする動画を作成しました(2023/10/1)
レケンビ点滴のはたらき、効きめをお伝えする動画を作成しました。
アルツハイマー病進行抑制薬「ドナネマブ」をイーライリリーが厚生労働省へ承認申請(2023/9/28)
イーライリリーは、アルツハイマー型認知症治療薬「ドナネマブ」について、厚生労働省に承認を求める申請を行いました。
ドナネマブは、エーザイが発売したレケンビ点滴と同様に「アミロイドβ」にくっついて、取り除く「抗体医薬」であり、治験データではドナネマブを投与された群は、投与されていない群と比較して1年半後の認知機能低下が35%抑えられたという効果が確認されています。
アルツハイマー病進行抑制薬「レケンビ点滴静注用200mg/500mg」(成分名:レカネマブ)が承認されました(2023/9/26)
2023年9月25日、厚生労働省は新医薬品としてレケンビ点滴静注用を承認しました。
日本での承認は、2023年7月の米国フル承認に次いで、世界で2か国目となります。
投与に際しては、PET診断や脳脊髄液での病理を確認することが必要条件となっています。
効能・効果:「アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制」
対象:「ADによる軽度認知障害(MCI)及び軽度の認知症(総称して早期AD)」
用法・用量:「通常、レカネマブ(遺伝子組換え)として10mg/kgを、2 週間に1 回、約1時間かけて点滴静注する」
としており、進行を抑制する効果があるだけで、既存のアルツハイマー病を治癒する効果はないことをご了承ください。
そのため、脳内アミロイドβプラークの可視化を目的としたPET画像検査用の放射性診断薬「ビザミル静注」「アミヴィッド静注」について効能を追加することが承認されました。
レケンビ点滴静注の薬価どの程度になるでしょうね。米国では1年間投与すると一人の患者さんに使用する薬代が2万6500ドル(380万円)程度と報じられています。
2週に1回使用する薬ですので、1回あたりの薬価は15万円程度となるのでしょうか? レケンビ点滴の薬価にも注目が集まりそうです。
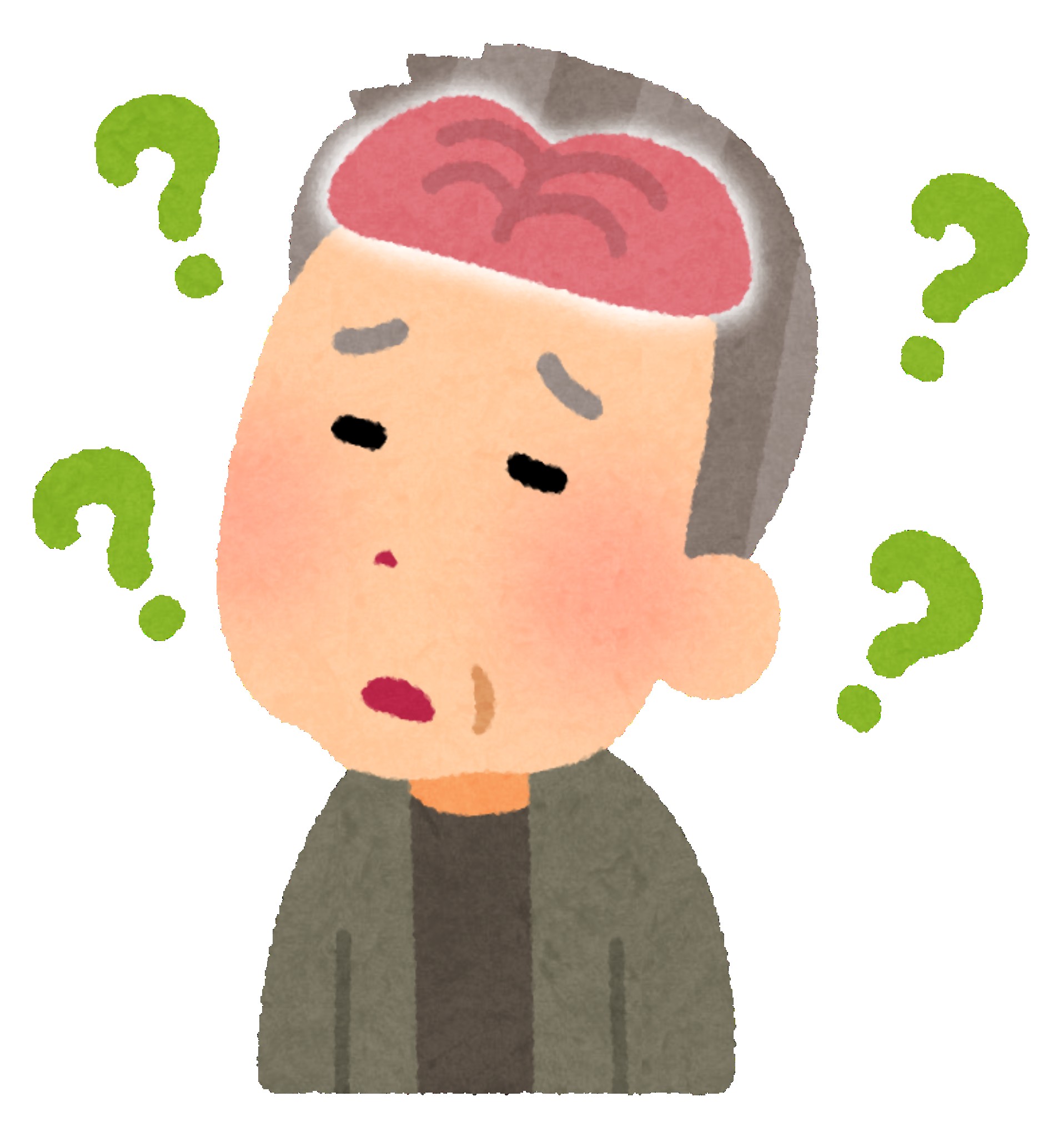
nintisyo
アルツハイマー病進行抑制薬「レケンビ点滴静注用200mg/500mg」(成分名:レカネマブ)の承認を審議(2023/8/8)
アルツハイマー病進行抑制薬「レケンビ点滴静注用200mg/500mg」(成分名:レカネマブ)が2023年8月23日に行われる厚生労働省の薬食審・医薬品第一部会にて承認可否が審議されます。
適応症は「アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制」です。
薬理作用は、抗アミロイドβプロトフィブリル抗体製剤であり、アルツハイマー病の原因物質とされる神経毒性をもつ可溶性のアミロイドβ凝集体に選択的に結合し、脳内から除去することでアルツハイマーの症状進行を抑制する疾患修飾作用を持つとされています。
2023年8月23日「厚生労働省:薬食審・医薬品第一部会にてレカネマブ」の承認可否が審議
アルツハイマー病進行抑制薬「ドナネマブ」の治験データ(2023/8/6)
米国ではエーザイが開発したアルツハイマー病治療薬(抗体薬)のレカネマブが正式に医薬品として承認され、日本国内でも承認審査が行われている状況です。エーザイ以外の会社としては、米国のイーライリリー社が早期アルツハイマー病の患者を対象とした抗体薬「ドナネマブ」に関する治療成績を公開しましたので、以下に記します。
イーライリリー:早期アルツハイマー病患者へドナネマブを投与した臨床試験データ(日本語)
アミロイドβタンパク質に対するモノクロナール抗体「ドナネマブ」について
イーライリリーがアルツハイマー病治療薬として開発した製剤で、第三相臨床試験が終了したところです。
ドナネマブ:脳内で蓄積されたアミロイドβタンパクに対するモノクロナール抗体で、標的となるタンパク質にくっつくと、ミクログリアによる貪食を誘導することで、アミロイドβタンパク質を除去する作用が期待される製剤です。
第三相試験データ
対象:65~85歳の軽度認知障害または軽度認知症患者(平均年齢73歳)
ミニメンタルステート検査にて20~28点の患者が対象です。(数値が小さくなるほど、認知症が進行していることを示します)
被験者1736を1(860人):1(876人)に振り分けて、4週間隔でドナネマブ薬またはプラセボ薬を静注します。
ドナネマブの投与方法は最初の3回はドナネマブ700mg、それ以降は1400mgを投与しています。
投与開始から76週後(約1年半後)の認知機能を評価しています。
結果
iADRSスコア(認知および日常生活を評価する:値が小さいほど、認知症が進行している指標)によると投与開始前と比較して76週時点における認知度は
ドナネマブ群:-6.02
プラセボ群:-9.27
となり、1年半で認知機能がどちらも低下していることがわかりますが、その低下率はプラセボ群でより大きくなっていることが見て取れます。
病状の進行としてはドナネマブを投与することで35.1%抑制できた(進行を遅らせることができた)と評価します。
次に、CDR-SBスコア(認知症の重症度を評価する:値が大きいほど認知症が進行している指標)
ドナネマブ群:1.2
プラセボ群:1.88
となり、プラセボ群で認知症の重症度がより進行していることが見て取れます。ドナネマブを投与することで認知症の進行を28.9%遅くすることができたと評価します。
脳内のアミロイドβタンパク質の蓄積量
アミロイドPETとう検査方法を用いて、投与から76週時点におけるアミロイドβタンパク質の蓄積量を評価しています
ドナネマブ群:88.0センチロイドを減少させた
プラセボ群:0.2センチロイド増えた
脳内に蓄積していたアミロイドβタンパク質の量に関しては、ドナネマブを投与することで、薬理作用通り減少させることに成功しています。一方でプラセボ群ではアミロイドβタンパク質が増えています。
以上のデータより、軽度認知症患者を対象としてドナネマブを投与すると、脳内に蓄積するアミロイドβタンパク質を減らして、アルツハイマー型認知症の進行を遅らせることができたとまとめています。
米国でアルツハイマー治療薬「レカネマブ」を投与するとタウタンパクの蓄積を遅延させる(2023/7/21)
エーザイが米国で発売しているアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」に関して、最新の解析が発表されました。
タウPETを用いた脳内のタウ病理に関する発表によると、レカネマブを投与することで側頭葉におけるタウ病理の蓄積が遅延することが報告されました。またアルツハイマー病の初期段階を示す脳内タウの蓄積量が軽度な集団では、顕著な臨床効果が認められたことが報告されました。
タウタンパクはアルツハイマー病をはじめとする神経変性疾患で脳に蓄積して、神経細胞の死を招くタンパク質であり、タウの蓄積を抑制することにより神経細胞死を抑制させる効果が期待されます。
レカネマブはアミロイドβタンパク質に対する抗体薬なわけですが、タウタンパク質の蓄積を遅らせる効果も期待できるのであれば、非常に有益な薬剤となりうる可能性を秘めているのかもしれません。
エーザイ「アルツハイマー病/認知症領域の開発品に関する最新データを発表 」
米国でアルツハイマー治療薬「レカネマブ」をFDAが正式に承認(2023/7/16)
米国のFDAはアルツハイマー治療薬「レカネマブ」について、2023年1月6日に迅速承認という形で承認しておりましたが、承認後も有効性の評価を継続し、2023年7月7日に正式承認とすることを発表しました。
レカネマブ注射(商品名:LEQEMBI」は脳内に蓄積したアミロイドβタンパク質の凝集体に対するモノクロナール抗体であり、アミロイドβタンパク質を除去する効果が期待される医薬品です。
FDAがレカネマブの有効性を評価したデータは「CLARITY AD(301試験)」です。
CLARITY AD(301試験)
軽度認知障害または軽度認知症のアルツハイマー病患者1795名をレカネマブ群とプラセボ(偽薬)群に1:1に割り付けた臨床データです。
レカネマブは体重1㎏あたり10mgの用量を2週間に1回て投与する製剤で、18カ月後までの効果を評価しています。
認知症の臨床的認知症尺度としてCDR-SBスコア(値が大きいほど認知症が進行している)が使用されました。
結果
レカネマブ群:治療開始前:3.2→18カ月後:1.21
プラセボ群:治療開始前:3.2→18カ月後1.66
また、レカネマブ投与群では症状の悪化が27%抑制されたことが報告され巻いた。
脳内に蓄積したアミロイドβタンパク質の量を比較した試験では、レカネマブ投与群で59.1センチロイドの減少が確認され、レカネマブを投与することで、脳内のアミロイドβタンパク質が減少し、軽度認知障害または軽度認知症に対する有効性が示されました。
上記のデータを評価し、米国ではFDAがレカネマブを正式承認しました。日本国内では「レカネマブ」を厚生労働省が優勢審査品目に指定し承認審査が行われています。
レカネマブを2週に1回投与した場合、1人当たりの年間薬剤費は600万円とも言われていますので、厚生労働省が費用対効果をどのように評価するか、今後の情報に期待したいです。
アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」をエーザイが厚生労働省の優先審査品目に指定されました(2023/1/31)
2023年1月16日にエーザイはアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」を厚生労働省に承認申請しましたが、1月30日に厚生労働省より「優先審査品目」に指定されたことを同ホームページに公開しました。
優先審査品目とは重篤な疾病で医療上の有用性が高いと認められた新薬に与えられて、総審査期間が短縮されるルールが適応されます。
通例では医薬品の総審査期間は12カ月程度なのですが、優先審査が行われると、総審査期間の目標が6カ月に短縮されます。また、前段階の事前評価による審査も前倒しで実施されます。
アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」をエーザイが日本国内で承認申請しました。(2023/1/17)
エーザイは早期アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」について国内新生をしたことを同ホームページに公開しました。
レカネマブはすでに米国FDAにて2023年1月6日に医薬品承認されており、欧州では2023年1月9日に申請を行っていましす。
中国には2022年12月にデータ提出を行っており、米国以外での承認取得を目指しています。
米国では2023年1月18日にレカネマブの発売が開始されました。価格は年間2万6500ドル(薬350万円)です。
アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」が米国FDAに承認されました。(2023/1/7)
米国食品医薬品局(FDA)はバイオジェンとエーザイが共同開発していたアルツハイマー型認知症の治療薬「レカネマブ」を承認しました。
商品名は「Leqembi 」です。
「Leqembi」はアルツハイマー型認知症の方の脳に蓄積するβアミロイドという蛋白質の凝集を標的とするモノクロナール抗体です。投与により標的となったβアミロイドが異物と認識され、マクロファージや好中球によって除去される効果が期待される製剤です。
体重1㎏あたり10mg量を2週間ごとに静脈内注射する製剤です。
臨床試験における副作用は、頭痛・視覚障害・錯乱が報告されています。
また、脳出血の発症リスクが17%(プラセボ群で9%)で報告されています。
FDAはレカネマブの承認にあたり、アミロイド関連の画像異常と出血リスクについて添付文書に警告が含まれると記しています。
アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」投与後の脳出血死亡例について(2023/1/3)
2023年1月6日に米国食品医薬品局(FDA)がアルツハイマー型認知症「レカネマブ」を医薬品として承認するかどうか判断することになっています。
また医薬品として承認するにあたり、使用する条件を課すことも検討されています。
アルツハイマー型認知症治療薬として抗アミロイドβに対するモノクロナール抗体「レカネマブ」が医薬品として承認されるか注目が集まりますが、ここではレカネマブと抗凝固薬を投与されて死亡した2例について症例を把握します。
(開発元のエーザイは「特定患者の死亡例に関して、原因を特定することは難しい」と見解を述べていますので死亡例についてレカネマブと抗凝固剤との因果関係は不明でであることはご留意ください。)
脳アミロイド血管症とレカネマブについて
CAA-β-amyloid
上の写真は、ヒトの脳の前頭葉における血管の顕微鏡写真です。
青色がβアミロイド、赤色が血管平滑筋、緑色が血管膜です。
アルツハイマー型認知症により脳内にβアミロイドが蓄積していくと、脳内血管においてβアミロイド(青色)が血管平滑筋(赤色)に置き換わることが示唆されています。
血管平滑筋がβアミロイドに置き換わると、血管膜(緑色)は炎症を起こして弱くなり、血管がもろくなります。この状態を脳アミロイド血管症と呼びます。
「レカネマブ」はβアミロイドを「異物」と認識させる抗体です。βアミロイドにレカネマブがくっつくと、ヒトはレカネマブがくっついたβアミロイドを「異物」と認識して除去します。βアミロイドはアルツハイマー型認知症の原因タンパクの一つと考えられていますので、それ除去されれば認知症の進行速度が抑えらえると考え、「レカネマブ」が考案されたわです。
では、脳アミロイド血管症の被験者にレカネマブが投与されるとどうなるでしょうか。血管平滑筋のに置き換わりβアミロイドが配置されている血管に対して、レカネマブが投与されると、血管を形成しているβアミロイドが「異物」と認識されて除去されるわけですね。すると、血管周囲がスカスカ・ボロボロになるわけですね。
この状態で血液の凝固を抑える薬(血液サラサラの薬)を使用すると、ボロボロの血管を修復できなくなり、破裂して大量出血が起こるわけです。
第三相試験中にレカネマブを投与された80代後半の男性はエリキュース錠(抗凝固剤)を飲んでおり脳出血で死亡しました。
死亡2例目の65歳女性は脳卒中で緊急搬送され、tPA(血栓溶解剤)を投与された後、脳の全体にかなりの出血が生じで死亡しました。
開発元のエーザイは、レカネマブの治験を行うにあたり、「微笑出血や重篤な脳アミロイド血管症」の兆候がある被験者は、治験対象から除外しています。
しかし、脳アミロイド血管症を有する被験者を完全に特定することは難しく、重篤な脳アミロイド血管症を有する被験者が治験スクリーニングからすり抜けて治験枠に入ってしまったことが原因ではないか?と研究者は考察しています。
実際、脳アミロイド血管症は加齢により有病率が増加しており、30~40%の高齢者で認めらえているという報告があります。また、アルツハイマー型認知症の患者では80~90%で脳アミロイド血管症の病理所見が認められています。
日本国内の解剖例の検討によると60歳代で33%、70歳代で53%、80歳代で54%、90歳以上で74%に脳アミロイド血管症が認めれたという報告があります。
(脳アミロイド血管症に関しては、アミロイド沈着そのものに対する治療はなく、有効性の確立された治療方法もありません。)
ということで、上記をまとめますと
アルツハイマー型認知症の患者さんの脳血管にはβアミロイドが付着しており、脳血管を形成している血管平滑筋とβアミロイドが置き換わってるケースが報告されています。
(なぜ、置き換わるかについては不明ですが、血管平滑筋は筋肉ですので、アミノ酸が集まって作られた蛋白質です。βアミロイドも「不要蛋白質が凝集したもの」ですので、どちらも蛋白質という意味では「置き換わる」要因の一つなのかもしれません。(個人的な感想です))
アルツハイマー型認知症の患者のうち80~90%は脳アミロイド血管症を有しているという報告があります(程度は異なる)
レカネマブはβアミロイドを除去する作用を有した薬剤であるため、血管に組み込まれた「βアミロイド」を徐々してしまい血管がボロボロになる可能性があります
抗凝固剤とレカネマブを併用した被験者2例で、大量の脳出血により死亡した可能性が検討されている
いずれにしても、開発元のエーザイは2例の死亡例について「レカネマブが原因ではない」とコメントをだしておりますので、上記はあくまでも検討の一つであることをご留意ください。
アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」は症状悪化の抑制効果あり(2022/12/2)
エーザイはアルツハイマー病の治療薬「レカネマブ」について新たなデータを公開しました。
最終段階の臨床試験において「症状の悪化を抑制する効果があった」とするデータをまとめました。
レカネマブの早期アルツハイマー病に対する臨床第Ⅲ相試験データ
治験対象者1795人(平均年齢72歳)のうち、レカネマブ投与群(898人)と偽薬投与群(897人)に振り分け、2週間に1回、18カ月間にわたり静脈注射が行われました。
認知症の臨床的認知症尺度としてCDR-SBスコアが使用されており、ベースライン時(治験開始前)のスコアは両群ともに3.2でしたが、投与18カ月後のベースラインからの変化はレカネマブ投与群で1.21、プラセボ群で1.66でした。
その結果、レカネマブ投与群では症状の悪化が27%抑制されたことが報告されました。また「ADCOMS」と言われる早期アルツハイマー病の進行度を示す指標でも進行が24%抑制されたことが報告されました。
脳内に蓄積したアミロイドβタンパク質の量について、偽薬投与群では増加したにもかかわらず、レカネマブ投与群では大幅に減少される効果が認められました。(レカネマブ投与群で、マイナス59.1」センチロイド)
副作用に関しては、レカネマブ投与群の12.6%で脳の浮腫、17.3%で脳の出血が見つかっています。(大部分は軽症で発見4カ月後に消失しています)
また、18カ月以降もレ投与を希望したレカネマブ投与群1608人中2人が脳出血死亡しています。(偽薬投与群897人中1人が脳出血で死亡しています)
エーザイによると、脳出血で死亡した2人には合併症があり、脳梗塞の治療などに使用される抗凝固薬を併用していたたとして、「レカネマブが原因ではない」という見解を示しています。
アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の効果について(2022/10/1)
アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」が、治験データによると投与開始から1年半(18カ月)で症状悪化を27%抑制した!
とNHKで報道されていました。
アルツハイマー病の症状悪化を抑える新薬登場か?2023年3月末までにアメリカと日本、EUでの承認申請を行うとしており、この部分だけを切り抜いて読むと、すごい薬が出てくるようにも思えますが、ちょっと情報に偏りがあるように感じましたので、私なりの解釈を記します。
レカネマブ
アルツハイマー病患者の脳内に蓄積することが報告されているβアミロイド蛋白質に対する抗体としての役割がある治験薬です。
ベータアミロイドにレカネマブがくっつくと、私たちの体は「異物」と判断して、レカネマブがくっついたβアミロイドを取り除く効果が期待される製剤です。
(ヒト化モノクロナール抗体と呼ばれます)
エーザイの臨床データを確認してみると
治療対象者は「軽度認知障害」および「軽度(初期)認知症」の方が治療対象者となっています。
~軽度認知障害~
「記憶力、注意力などの認知機能に低下がみられるが、日常生活に支障をきたすほどではない状態」
(周囲の人が気づかないレベル)
~軽度(初期)認知症~
「物忘れを感じる、名前がでてこない、計画性が低下する、文章が覚えられない」
(周囲の人が気づくレベル)
上記のような方に対してレカネマブを投与したところどうなったか?というのが治験データです。
実際のデータとしてはレカネマブを1年半(18カ月)、2週に1回、10mg/kgを投与した場合、投与しなかった群と比較して認知症の進行を27%抑えられ有効性が確認された。というものです。
また、レカネマブの投与から6カ月以降、すべての評価ポイントにおいて、プラセボ群と比較して悪化抑制を示したと報告されています。
(第二相臨床データでは、プラセボ群と比してレカネマブを投与した群では80%以上の確率で認知症の進行を25%抑えることが報告されていますので、今回の第三相臨床試験(被験者1800人)と、だいたい同じ感じですね)
レカネマブ投与による有害事象に関しては、脳浮腫の発現率が12.5%(プラセボ群では1.7%)、脳微小管出血が17%(プラセボ群では8.7%)でした。
(レカネマブ投与におけるアミロイド関連画像異常の発現率:21.3%(プラセボ群では9.3%))
ということで、レカネマブは現在認知症の患者さんではなく、これから認知症になるかも?という方を対象とした医薬品であるということです。
気になるお値段についてはわかりませんが、参考までに記しますと、開発された製剤が「医薬品」として国に認可されると「薬価(医薬品の値段)」が決まります。
米国にて、レカネマブと同じ薬理作用をもつ医薬品「アデュカヌマブ」が一足先にFDAにより認可を受けたのですが、その時の薬価は「アデュカヌマブを月に1回、1年間投与すると600万円程度」と報道されていました。
同様の薬理作用をもつ「レカネマブ」が医薬品として承認されるかは不明ですが、どうでしょう、医薬品として承認されれば、それ相応の「薬価」がつくかもしれません。
アルツハイマー病の原因が解明か?脳内に咲く「毒の花」に不要蛋白質が蓄積(2022/6/12)
どうやらアルツハイマー病の原因が判明したようです。
インパクトファクター25前後の非常に影響力の大きな「Nature Neuroscience」にアルツハイマー病モデルマウスを用いた実験により、タンパク質の分解がうまくいかずに不要蛋白質が蓄積される経過が報告されました。
[pc]
[/pc] [sp]
[/sp]
アルツハイマー病の原因はリソソームのpH異常が原因(マウスのデータ)
今回の報告では、以下の2つのワードがポイントとなりますので、先に単語の意味を記します。
・オートファゴソーム
細胞内で、異常な蛋白質、壊れた細胞内小器官、過剰な蛋白質、微生物などの不要物を包み込む球状の構造体
不要物を自身の球体に確保したオートファゴソームはリソソームと合体して、不要物質をアミノ酸レベルまで分解し、再利用します。
・リソソーム
自身の内側にpH5前後の酸性下して、様々な加水分解酵素を保有しています。リソソームのを形成する膜にはvATPaseと呼ばれる出入口が作られており、ここから水素イオンを取り込むことでリソソームの内側を”酸性”状態に維持しています。
オートファゴソームとリソソームが合体すると、リソソーム内に含まれた酸性・加水分解酵素により不要蛋白質が分解されます。
上記のオートファゴソーム・リソソームの働きを踏まえた上で、アルツハイマー病マウスの脳内状態を確認してみます。
アルツハイマー病マウスの脳内にあるリソソームの状態を確認したところ、vATPase活性が低下しており、リソソームの内側が酸性状態を維持できない状態でした。「酸性じゃないリソソーム」とオートファゴソームが合体したところで、オートファゴソームが取り込んだ不要な蛋白質を分解することはできません。
以下の写真をごらんください。蛍光ラベルされた黄色い点の集まりが確認できます。これが「酸性じゃないリソソームとオートファゴソームが合体したもの」の集合体です。

PANTHOS
細胞核の周囲に「酸性じゃないリソソームとオートファゴソーム」の凝集体が付着し、花びらのような状態を形成していることがわかります。
筆者らはこの状態を「PANTHOS(毒の花)」と表現しています。
さらに、この凝集体の内部をしらべると、これまでアルツハイマー病の原因と考えられていた「アミロイドβタンパク質」が徐々に蓄積していることが確認されています。
「酸性じゃないリソソーム」はアミロイドβタンパク質が細胞外に沈着する4カ月以上も前から確認されていました。
以上のことから、アルツハイマー病の原因は「リソソームの内腔が酸性じゃなくなる」ことで細胞内の不要物質を分解することが出来なくなり、オートファゴソームと酸性じゃないリソソームが合体した凝集体が蓄積することが原因であることが示されました。
筆者らはリソソームの酸性化を管理するvATPaseの異常が本質的な原因であると捉え、リソソームpH障害を薬理学的標的とすることがアルツハイマー病の治療となりうると示唆しています。
生活習慣病とアルツハイマー型認知症の発症リスクについて
35歳以上の被験者を対象として、血糖値・血圧・脂質異常症のリスクと将来のアルツハイマー型認知症の発症リスクについての大規模疫学研究が報告されていましたので、以下に記します。
生活習慣病とアルツハイマー型認知症の年代ごとの発症リスク
被験者:4932人
35歳~50歳、51歳~60歳、61歳~70歳という3群に分類し、長期期間の観察を行って血糖値、血圧、脂質異常値がアルツハイマー病の発症リスクにどのような関係があるかを調査したデータです。
35~50歳群:35.2±8.9年間の追跡調査を行い、5.5%がアルツハイマー型認知症を発症しました。
35~50歳群におけるアルツハイマー型認知症との関連因子
善玉コレステロール(HDL-C)が15mg/dl高いごとにアルツハイマー型認知症の発症リスクが15%減少することが示されました。
中性脂肪の値が高いほど、アルツハイマー型認知症の発症リスクが高いことが示されました。
血糖値および拡張期血圧(下の血圧)とアルツハイマー型認知症との関連は見られませんでした。
51~60歳群におけるアルツハイマー型認知症との関連因子
善玉コレステロール(HDL-C)が15mg/dl高いごとにアルツハイマー型認知症の発症リスクが18%減少することが報告されました。
血糖値が15mg/dl高いごとにアルツハイマー型認知症の発症リスクが15%上昇することが報告されました。
中性脂肪および拡張期血圧(下の血圧)とアルツハイマー型認知症との関連は見られませんでした。
61~70歳群におけるアルツハイマー型認知症との関連因子
血糖値が15mg/dl高いごとにアルツハイマー型認知症の発症リスクが7%上昇することが報告されました。
拡張期血圧(下の血圧)が高いほど、アルツハイマー型認知症の発症リスクが上昇することが報告されまた(リスク比14%)
善玉コレステロールおよび中性脂肪とアルツハイマー型認知症の関連はみられませんでした。
以上の結果を受けて、将来の認知症のリスクを抑えるためには、30代のころからコレステロール値や中性脂肪の値に配慮する必要があるようです。
また、年代によって関連リスクが変化していることから、生活習慣病の予防は継続的に続けていくことが、将来のアルツハイマー型認知症の発症リスクを下げることにつながることが示唆されると筆者らは考えています。
脂質異常とアルツハイマー型認知症との関連報告としては、HDL(善玉コレステロール)は血管内のアミロイドβタンパク(認知症の原因と考えられる1つのタンパク質)を減少させ、アミロイドβによる血管内皮における炎症を抑えることが報告されています。また、アミロイドβタンパクの線維化を遅延させるという報告もあります。
血糖値とアルツハイマー型認知症の関連報告としては、高血糖状態が続くとアストロサイトを介した神経炎症・神経損傷を悪化させ、アルツハイマー型認知症のリスクを上昇させることが示唆されています。また高血糖状態はタンパク質の糖化をもたらし、マクロファージ遊走阻止因子の糖化および酸化を介して、自然免疫系の調節システムに影響を及ぼし、アルツハイマー型認知症を進行させる可能性があります。また、インスリン抵抗性が進むと、精神機能を悪化させ、脳内のインスリン取り込みが減少し、脳細胞間のシグナル伝達を阻害して、記憶に影響を及ぼす可能性が示唆されています。
ドネペジル経皮吸収型製剤を「興和」がライセンス契約、製造販売承認申請(2022/4/22)
アリセプトD錠の経皮吸収型製剤についての情報です。
ドネペジル経皮吸収型製剤について、興和薬品が独占的販売権に関するライセンス契約を締結しました。ドネペジル経皮吸収型製剤に関しては「帝国製薬」が2022年1月に厚生労働省に製造販売承認申請を行っておりましたが、興和薬品は帝国製薬の承認取得後に、上記のライセンス契約に基づき、国内での独占販売を開始するとしています。
認知症進行抑制に関しては、アリセプトD錠やそのGE錠が使用されていますが、嚥下困難や胃腸障害などの副作用によって治療継続が難しい方が多くおられます。
同一成分の貼付剤が発売されることは、治療の選択肢が増えることとなりますので、患者様にとって有益であると感じます。
お昼寝の時間&回数とアルツハイマー型認知症の進行には双方向の関係がある
高齢者を対象として、お昼寝の時間・回数とアルツハイマー型の進行に関する興味深いデータを拝見しましたので、以下に概要を記します。
[pc]
[/pc] [sp]
[/sp]
昼寝とアルツハイマー型認知症の関係について
参加者:1065(平均年齢:81.4歳、男女比:女性76.6%)
1日の平均昼寝時間:46.6分
昼寝の頻度(回数):1.8回(0.9回~3.35回)
夜の総睡眠時間:5時間40分
昼寝の判定方法
利き手ではない方の手首に測定器を着け、午前9時~午後7時までの間に、眠った時間・回数を「昼寝」と定義しています。(平均10日前後、上記の測定を行い、昼寝の平均値を算出しています)
昼寝に関するデータ
・昼寝の時間と昼寝の回数には正の相関があり、昼寝の時間が長い人は昼寝の回数も多いことがわかりました。
・昼寝の時間・昼寝の回数は年齢と正の相関があり、年を重ねるほど昼寝の時間・回数が増えることがわかりました。
・昼寝の時間・頻度について男女による性差はありませんでした。
調査データ開始時、1065人が参加し、そのうち812人は認知障害なし、209人が軽度認知障害、44人が認知症と診断をうけていました。
調査期間中に
「認知症障害なし」であった812人のうち384人が軽度認知障害を発症し、146人がアルツハイマー型認知症を発症しました。
「軽度認認知障害」であった209人のうち101人がアルツハイマー型認知症を発症しました。
調査期間中に、昼寝の時間は加齢とともに1年あたり11.31分増加が確認されました。非常に興味深いことに、軽度認知障害と診断をうけた被験者では1年あたりの昼寝の時間が24.66分の増加が確認されました(2倍)。さらに、アルツハイマー型認知症と診断をうけた被験者では1年あたりの昼寝時間が68.35分と6倍程度まで増加したことが確認されました。
同様に、昼寝の回数に関しても、加齢とともに1年あたり0.35回の増加が確認されました。軽度認知障害と診断をうけた被験者では1年あたりの昼寝の回数が0.67回へ増加し、アルツハイマー型認知症と診断をうけた被験者では1年あたりの昼寝の回数が1.25回へ増加したことが報告されました。
昼寝の時間とアルツハイマー型認知症発症についてのリスクをデータ
・調査開始時点ではアルツハイマー型認知症ではなかった被験者のうち6年以内にアルツハイマー型認知症を発症した割合は24%であった
・1日1時間以上の昼寝(長時間昼寝)をする人は、1日1時間未満の昼寝(短時間昼寝)をする人と比較して、認知症発症リスクが1.4倍増加する
・1日1回以上昼寝をする人は、1日1回未満の昼寝をする人と比較して、アルツハイマー型認知症を発症するリスクが1.4倍増加した
・年を1歳とることで、認知症発症リスクは1.12倍に増える
筆者らは上記のデータを踏まえ、「アルツハイマー型認知症の進行が昼寝の時間・回数を2倍以上に増加させて老化を加速させると同時に、昼寝の時間・頻度が増加することがアルツハイマー型認知症の発症リスクをさらに高める」とまとめています。
つまり、「昼寝」と「アルツハイマー型認知症」は相互に症状を進行させる要因であると示唆しています。
ここで少し余談ですが、「昼寝をするから夜眠れなくなるのではないか」「夜に睡眠薬を飲んでぐっすり眠れれば、昼寝の時間を減らすことができるのでは?」といった改善策がイメージできそうですが、「昼寝とアルツハイマー型認知症」に関しては、そうではないようです。
被験者は調査期間中、手首に24時間にわたり測定器をつけて生活しており、昼寝時間だけでなく夜間の睡眠時間も計測されています。今回のデータの有用な点として「夜間の睡眠の量・質を調整したうえで、昼寝とアルツハイマー型認知症には相互相関がある」と結論づけている点です。
言いかえますと、夜間の睡眠状況の変化とアルツハイマー型認知症発症との直接的な関連は観察されなかったにもかかわらず、「昼寝の時間・回数の増加とアルツハイマー型認知症の進行には相互の関係が確認された」という点がポイントとなります。
筆者らは上記の理由として、アルツハイマー型認知症発症が進行すると、脳内におけるタウタンパク質の量が増し、覚醒促進ニューロンの病的損傷による覚醒不全が昼寝の増加を加速させるのではと記します。アルツハイマー型認知症や軽度認知障害の患者では、脳波計による微細な睡眠パターンが計測されるというデータも報告されており、「昼寝時間の延長」と「アルツハイマー型認知症の進行」は双方向の関係があるのではと示唆しています。
昼寝とアルツハイマー型認知症の関係について
メマンチンやドネペジル、ガランタミンなどの認知症治療薬を飲んでいる患者様のご家族から「お昼ご飯を食べた後、目を離すと昼寝をしています」「午前も午後もウトウトと昼寝をしています」といったお話しを伺うことが多々あるのですが、そのようなご家族の話を詳しく伺うと、「昼寝は何度もします。夜も眠れています。」という回答が多いように日ごろ感じていました。
「我慢できずに何度も昼寝をするが、夜も眠れる」のは脳に異常タンパク(タウタンパク・アミロイドタンパク)が蓄積したことによる「覚醒神経損傷」「覚醒ニューロンOFF」と考えると合点がいきます。
若いころに「今日は昼寝をしたから、夜に全然眠れない」といのは脳が元気な証拠なんだろうなぁと思い返しました。
頭痛と認知症の関係について
2001年~2020年までに公表された頭痛と認知症のリスクについての研究12件、46万5358例をたいしょうとした解析によると
頭痛歴はアルツハイマー型認知症のリスクを35%上昇させる
頭痛歴は血管性認知症のリスクを72%上昇させる
頭痛歴を有する女性は男性よりも認知症リスクが32%高い
頭痛が認知症の発症に関して、独立したリスク因子であることを示唆している
上記のメタ解析が報告されました。(2022/2/11)
アルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」の効果について
2022/1/13追記)
米国公的医療保険を管轄するCMSは2022年1月11日に、エーザイと米国バイオジェンが共同開発したアルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」について、臨床試験参加者のみの保険適用を認める指針案を発表しました。
これにより「アデュカヌマブ」の公的保険適用が一部の人に限られることとなるため、普及の妨げとなるみこみです。
今回の決定は暫定的なものであり、30日間のパブリックコメントを募る期間が設けられております。最終決定は2022年4月11日に下される見込みです。
アデュカヌマブの承認申請に関しては、承認された当時から効果について疑問の声があがっていました。
以下は2021年10月に記載した記事です
軽度アルツハイマー病患者に対しては4週に1回アルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」を投与したデータが公開されました。
投与量は低用量(3~6 mg/kg)または高用量(6~10 mg/kg)のいずれかとして、4週に1回静脈内投与がおこなわれました。最大で1年半(20回)の投与を行ったEMERGE試験の結果です。
[pc]
[/pc] [sp]
[/sp]
アデュカヌマブを投与することにより、患者1人当たり生涯にわたりる質調整寿命(QALYs)をプラセボと比較して0.65増加させることが確認されました。さらに、介護者のQALYsを0.09減少させることも報告されました。認知症治療は本人だけでなく介護者の負担も大変ですので、介護者の負担軽減が確認されたことは有益なデータと感じます。
また、アデュカヌマブの投与により、アルツハイマー型認知症に移行する生涯確率が低下し、中等度アルツハイマー型認知症へ移行するまでの期間は、プラセボ群が4.92年だったのに対して、アデュカヌマブを投与した群では7.5年に延長することが確認されました。
また、施設入所に移行する生涯確率に関しても、
アデュカヌマブを群:25.2%対プラセボ群29.4%
と低下しているうことが確認され、社会生活を送る期間の中央値が1.32年増加したことが示されました。
アデュカヌマブは現在アメリカにて医薬品として認可されておりますが(信憑性を疑う医療従事者もおります)、日本では認可されておりません。また年間の薬剤費が600万円を超える治療であるため、費用対効果および、医薬品として認可し続けることが妥当かについて検討が行われている製剤と私は解釈しております。
エーザイ「早期アルツハイマー病治療薬”レカネマブ”」を米国FDAへ段階的申請プロセス開始(2021/9/29)
エーザイはアルツハイマー病の治療薬「レカネマブ」について、米国FDAに対し、段階的申請のプロセスを開始したことを発表しました。迅速承認制度を活用するとしています。
同社が開発したレカネマブは、アルツハイマー病の一因と考えられている”可溶性アミロイドβ凝集体(プロトフィブリル)”(異常たんぱく質の凝集したもの)に対するヒト化モノクロナール抗体(異物と認識してくっつく抗体)という生物製剤です。
臨床Ⅱb相試験データ
アミロイドβの脳内蓄積が確認された早期アルツハイマー病患者856人を対象としたデータによるとレカネマブ10mg/kgを2週間に1ど、18カ月間投与したところ、PET画像にて脳内のアミロイドβ蓄積量がベースライン(投与開始時点)では平均1.37ユニットであったものが、0.306ユニットに減少し、被験者の80%以上で脳内アミロイド陰性化が確認されたとしています。
また、脳内アミロイドβ減少の程度と、アルツハイマー病の臨床症状の有効性評価(ADCOMS、CDR-SB、ADAS-cog)による悪化の抑制度合いは相関している発表しています。
エーザイが早期アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」をFDAへ早期申請
アルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」が米国で承認される(2021/6/8)
2021年6月7日、米国食品医薬品局「FDA」はアルツハイマー病治療薬として「アデュカヌマブ」を迅速承認しました。
アデュカヌマブとはアルツハイマー病の原因の一因と考えられる「アミロイドβ」を標的とする抗体医薬品です。アデュカヌマブを投与された被験者の脳内では、脳内のアミロイドβとアデュカヌマブ抗体がくっついて、マクロファージや好中球が「アミロイドβ+アデュカヌマ」を貪食する(食べる)ことにより、脳内のアミロイドβが除去されるという薬理作用を示します。
アルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」が米国で医薬品として承認される
早期アルツハイマー病患者を対象とした治験データによると、アデュカヌマブを投与した群では投与しなかった群と比較して約1年半後の認知機能の低下率が22%抑制されたことが示されています。
FDAは承認に際し、投与することでの効果を明確にするために、あらたなランダム化比較試験の実施を求めています。効果が確認されなければ、承認を取り消すことも視野にいれています。
投与量については、4週に1回、1mg/kgからスタートして10mg/kgへ徐々に増量していきます。半年ほどかけて維持量である10mg/kgへUPしていきます。
10mg/kgを維持量とした場合の年間薬剤費は日本円で613万4240円です(米国価格)。
早期アルツハイマー患者を対象と考えたとしても、日本の保険医療で、この医薬品を賄うと考えると恐ろしい金額にも思えます。
日本国内では2020年12月にバイオジェンが承認申請を厚生労働省に提出しています。
以下に、アルツハイマー病に対するアデュカヌマブの臨床データおよび、承認に至るまでの経緯を記します。
アルツハイマー病治療薬“アデュカヌマブ”を米国FDAが受理(2020/8/20)
米バイオジェンエーザイはアルツハイマー病治療薬候補「アデュカヌマブ」の申請がが米国食品医薬品局(FDA)に受理されたことを公開しました。
アルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」がFDAに受理される
アデュカヌマブの受理に関しては、優先審査の指定を受けており、審査終了目標日は2021年3月7日に定められています。
FDAは、迅速審査のもと、可能であればこの申請について早期に審査を完了する予定であると述べています。
アデュカヌマブは脳内のアミロイドβの除去を作用機序としており、臨床結果の改善をもたらすことが報告された薬剤です。
アルツハイマー病治療薬“アデュカヌマブ”を米国FDAへ申請(2020/7/8)
米バイオジェンとエーザイは7月8日、アルツハイマー病治療薬として臨床試験を行っていたアデュカヌマブ(抗アミロイドβ抗体)について、米国FDAへ医薬品としての申請を行いました。FDAは60日以内に申請の受理を判断する予定となっています。申請が受理された場合は、FDAによって承認審査が行われます。(承認が認可されれば抗アミロイドβ抗体としては初の医薬品となります)
臨床試験結果において、アデュカヌマブはアルツハイマー病における脳内アミロイドβを除去することで、臨床症状の悪化を抑制することが報告されています。軽度認知障害患者および軽度アルツハイマー病の患者を対象とした臨床試験では、アデュカヌマブ投与群において、記憶・見当識・言語などの認知機能悪化が有意に抑制され、金銭管理・家事(掃除・買い物・洗濯)や単独での外出などの日常生活動作の悪化抑制が確認されたと報告されています。
エーザイがアルツハイマー病治療薬アデュカヌマブをFDAへ申請
アルツハイマー病治療薬“アデュカヌマブ”が医薬品となりうるか?(2019/12/12)
米バイオジェンとエーザイが開発しているアルツハイマー病治療薬“アデュカヌマブ”は2019年3月時点では効果がない可能性があるとして治験が中止された経緯がありました。日本国内でも先が兼審査指定制度の対象品目の指定が取り消されていました。

しかし、大規模データ(3285人)の解析を行った結果、高用量のアデュカヌマブ(10mg/kg)1カ月に1回投与した群がプラセボ群と比較して“23%の症状の悪化抑制”が示され、主要評価項目を達成したことが報告されました。
記憶などの認知機能や生活機能、家族や介護者からの情報をもとにした情報などの評価基準としては
MMSE(ミニメンタル試験):15%抑制
ADAS-Cog13:27%抑制
ADCS-ADL-MCI(家族・介護者からの生活情報):40%抑制
[pc]
[/pc] [sp]
[/sp]
いずれもアデュカヌマブを投与した群で一貫して悪化抑制効果が示されています。
アミロイドプラーク沈着のイメージングではアデュカヌマブを投与した群はプラセボ群と比較して投与26週および投与78週時点でアミロイドプラーク沈着の減少が確認されています。アルツハイマー病臨床試験会議での報告によると、早期のアルツハイマー病患者らを対象にした治験データによると、薬を使用しなかった群(550人)に比べて、アデュカヌマブを使用した群(550人)では、約1年半後、認知機能の低下が22%抑制された。
アデュカヌマブによる主な副作用:頭痛症状
エーザイが早期アルツハイマー予防薬”BAN2401”の国内臨床治験開始(2021/1/24)
製薬大手のエーザイは早期認知症予防薬(注射製剤)としてBAN2401の国内臨床試験を行うことを公開しました。被験者は55~80歳の男女でアミロイドβタンパク質の脳内蓄積が確認されているものの、無症状の方を対象としています。2~4週に1回、4年間の投与による認知症発症率の違いが研究されます。
BAN2401とは
BAN2401はアミロイドβタンパク質の凝集体(認知症患者の脳内に蓄積しているタンパク質)に対するヒト化モノクロナール抗体です。BAN2401のイメージとしては、アミロイドβタンパク質に選択的にくっつく抗体という感じです。一般的に抗体がくっついたタンパク質は”異物”と認識されて、マクロファージによって貪食されます(マクロファージが処理・除去します)。BAN2401はアミロイドβタンパク質(神経毒を有すると考えられています)にくっついて、無毒化し、脳内から除去させることで、認知症の発症を遅らせることができるのでは?と考えられている化合物です。
(エーザイが、他方で研究しているアデュカヌマブとは異なります)。
臨床試験
世界1400人を対象として4年間の投与を行い新薬となりうるかについて研究が行われます。
被験者:アミロイドβタンパク質がの脳内に蓄積しているものの、認知症を発症していない無症候患者55~80歳の男女1400人をプラセボ群とBNA2401投与群にわけて調査されます
対象国:米国・日本・カナダ・オーストラリア・シンガポール・欧州
投与期間:2~4週に1回点滴、4年間(216週)
主要評価項目:アミロイドPET検査による脳内アミロイド蓄積変化
副次評価項目:タウPET検査による脳内タウ蓄積変化
この臨床試験は米国にて2020年7月14日に治験開始が行われており、日本では2021年2月に治験が行われる予定です。
一般的に、軽度認知障害が認められる10~15年ほど前の時点から、脳内にアミロイドβタンパク質が蓄積されていくことが報告されており、アミロイドβタンパク質の蓄積量がある一定量を超えた段階で、脳の萎縮・認知機能の低下が発症することが示唆されています。BAN2401の優れている点は軽度認知障害が確認される前段階でアミロイドβタンパク質の除去を可能にすることで、脳萎縮や認知機能低下を遅らせることが期待されている点です。
現時点での世界における認知症患者数は5000万人といわれていますが、2050年には約3倍の1億5000万人を超えることが試算されています。日本国内でも2025年には730万人が認知症患者となることが予想されており、認知機能の低下を早い段階で予防・遅延させることが、有益な治療方針となります。
[pc]
[/pc] [sp]
[/sp]


コメント