多発性硬化症患者にヒト(胎児)由来の胎児神経前駆細胞を投与した第1次相試験(2023/1/22)
多発性硬化症(中枢神経系の脱髄疾患)に関して、胎児由来の神経前駆細胞を移植した報告がありましたので下記します。
(イタリア・ミラノでの報告です。流産胎児由来の神経前駆細胞に関して倫理的にご配慮ください)
被験者:多発性硬化症患者12名
年齢18~55歳、疾患期間2~20年、神経症状評価尺度:6.5以上
流産した胎児(10~12週)から胎児由来の神経前駆細胞を取り出し、神経前駆細胞を培養して増殖します。
増殖した神経前駆細胞を0.7×106、1.4×106、2.8×106、5.7×106という4つの治療用量を設定し、細胞/体重の用量で1回髄腔内投与します、
投与に際し、腰椎穿刺により脳脊髄液を10mlほど除去後に、上記の濃度の神経前駆細胞を10ml(ヒト血清アルブミンを0.028%含む生理食塩水)投与します。
移植直前にメチルプレドニゾロン125mgを静脈内前投与しています。また、拒絶反応を未然に防ぐため移植7日前~96週目までタクロリムスを投与し、処置前日から35日間にわたりプレドニン50mgを経口投与しています。
さらに、感染予防としてアシクロビル、コトリモキサゾールを併用しています。
単回投与後、用量制限毒性が認められないことを確認し、3カ月の間隔をあけて高用量が投与されています。
結果
移植後3カ月後に髄液を調べた結果、移植した細胞の増加が認められました。
注入した神経前駆細胞の数と相関して脳および灰白質の体積減少率が有意に下がっていたことが示されました。
中枢神経系の神経保護を促進するCSF蛋白質のレベルが増加しました。
2年間のフォローアップ期間中に5名の患者でMRI病変を呈し、50%の患者さんで新たT2病変が確認されました。
投与された神経前駆細胞の数と新たなT2病変の数および体積との間に関連性は見つかりませんでしたが、移植に起因するMRI病変の活性化の可能性を否定することはできず今後の課題とされました。
安全性に関しては、有害事象は軽度または中等度でした。
移植前の4年間(EDSS+0.24点/年)と移植後の2年間(EDSS+0.13点/年)を比較したところ、神経症状評価尺度の変化率(傾き)が小さいようにも見て取れますが有意差はなく、より進行した病期では、EDSSよりも感度の高い9-HPTスコアが、移植後の2年間の追跡期間中に悪化したデータが示されており、神経前駆細胞を投与することの意義については慎重に分析する必要があるとしています。
また注入した胎児由来の神経前駆細胞の数とも有意な相関はありませんでした。
多発性硬化症と腸内細菌との関連について
理化学研究所の研究チームが、多発性硬化症の発症や進行促進に腸内細菌が関与している可能性について報告していますので下記します。
マウスによる実験によると、腸内細菌の1種”Lactobacillus reuteri”が多発性硬化症の原因となる自己免疫であるT細胞の増殖を促し、Erysipelotrichaceae科の菌が、T細胞による病原性を高めるのでは?ということを報告しています。2種類の菌が相乗的にT細胞による自己免疫疾患を促進して多発性硬化症(中枢神経系系の炎症)を増悪させていると示唆しています。
マウスによる実験方法としては、各マウスに(アンピシリン・バンコマイシン・ネオマイシン・メトロニダゾール)という抗生剤をそれぞれ投与してマウスの腸内細菌を駆逐したところ、アンピシリンを投与したマウスにおいて、小腸における免疫応答(サイトカイン17細胞)の活性が抑制されたとしています。各抗生剤が投与されたマウスの腸内細菌叢をそれぞれ調べた結果、アンピシリン投与マウスにおいてErysipelotrichaceae科の菌の量が非常に低下していることがわかりました。
(無菌マウスにErysipelotrichaceae科の菌を定着させるとサイトカイン17細胞の活性が促進されたことも報告しています)
上記に加えて腸内細菌の1つLactobacillus reuteriが発現するペプチド(タンパク)もT細胞の増殖を促進していることがわかり、この2種類の腸内細菌が相乗的にはたらいて中枢神経系系の炎症を増悪させた可能性を示唆しています。
多発性硬化症とヒトヘルペスウイルス6型Aに対する抗体との相関について
多発性硬化症(感覚障害・運動障害・視力低下など)は神経細胞を覆う髄鞘が自己免疫により障害されて生じる疾患と考えられていますが、その原因は判明しておりません。
ヒトヘルペスウイルスには様々な型が報告されておりますが、その中の一つヒトヘルペスウイルス6型Aに対する抗体の量が多い人で、多発性硬化症を発症するリスクが高いという報告をスウェーデンの研究チームが行っておりましたので詳細を確認してみました。
ヒトヘルペスウイルス
ヒトヘルペスウイルスには様々な型があります。
ヒトヘルペスウイルス1型:口唇ヘルペス
ヒトヘルペスウイルス2型:性器ヘルペス
ヒトヘルペスウイルス3型:帯状疱疹
ヒトヘルペスウイルス4型:伝染性単核症
ヒトヘルペスウイルス5型:CMV単核症
ヒトヘルペスウイルス6型:突発性発疹・壊死性リンパ節炎
ヒトヘルペスウイルス7型:突発性発疹
ヒトヘルペスウイルス8型:?
ヒトヘルペスウイルス6型には6Aと6Bという2種類に分別することができることはわかっていましたが、それを正確に区別することはできませんでした。また6Aと6Bではどのような疾患に関与しているかについても不明なままでした。
しかし昨今の技術開発により血液中の抗体レベルを分析することでヒトヘルペスウイルス6を6Aと6Bに区分することが可能となりました。その結果、「6Aに対する抗体量が多い方で多発性硬化症のリスクと相関する/6Bは小児の突発性発疹などの軽度の疾患を引き起こす」ことが報告されました。以下に6Aに対する抗体量と多発性硬化症に関する報告内容を記します。

多発性硬化症とヒトヘルペスウイルス6A抗体量の関係について
被験者(多発性硬化症患者8742人、対照群7215人)の採血データを用いヒトヘルペスウイルス6Aに対する抗体量(正確には“ヒトヘルペスウイルス6Aの前初期タンパクIE1Aに対する抗体量)を調べた結果、多発性硬化症患者は対照群と比較して抗体量が平均1.55倍高いことが示されました(有意差あり)。この傾向は年齢が若いほど顕著にしめされました。
ヒトヘルペスウイルス6Aの前初期タンパクIE1Aに対する抗体量(対照群の比較倍率)
30歳未満:1.8倍
30~39歳:1.56倍
40~49歳:1.48倍
50~59歳:1.46倍
60歳以上:1.64倍
上記のデータから多発性硬化症とヒトヘルペスウイルス6A前初期短タンパクに対する抗体量には正の相関があることが示されました。一方で6Bに対しては負の相関がある(0.74倍)と筆者らは述べています。
ヒトヘルペスウイルス6Aに対する抗体量の増加については、多発性硬化症を発症する前から、既に確認することができます。検査後に多発性硬化症を発症した478人に関する報告によると、発症前血液サンプルを調査したところヒトヘルペスウイルス6Aに対する抗体量が多い状態にあることが示されています。
多発性硬化症を発症する前段階におけるヒトヘルペスウイルス6Aの前初期タンパクIE1Aに対する抗体量(対照群の比較倍率)
20歳未満:3.38倍
20~29歳:2.29倍
30~39歳:1.51倍
尚、ヒトヘルペスウイルス6Aに対する抗体量の多さは多発性硬化症の再発および進行には関連しているものの、疾患の重症度には関連はみられませんでした。また抗体量は年齢とともに低下すること、喫煙が抗体量をUPさせる要因となっていることが報告されています。(喫煙は多発性硬化症の危険因子)
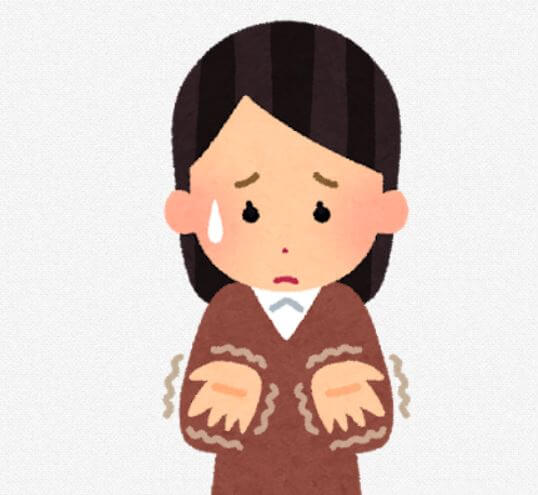
ms-hhv6a
ヒトヘルペスウイルス6Aが多発性硬化症を引き起こす?
ヒトヘルペスウイルス6Aも6Bもどちらも脳内に潜伏ことが可能ですが、6Aのみが「オリゴデンドロサイト」と呼ばれる細胞に潜伏・感染することが報告されています。「オリゴデンドロサイト」は髄鞘を形成するはたらきをもっています。多発性硬化症は髄鞘の損傷により引き起こされる疾患です。
「ヒトヘルペスウイルス6Aの生息域であるオリゴデンドロサイトへ自己免疫が攻撃を仕掛けること」
「オリゴデンドロサイトの減少により髄鞘の形成が阻害されること」
「髄鞘の修復作業が進まずに、髄鞘の欠損・障害が進行すること」
このあたりが多発性硬化症の要因なのでは?と筆者らは推測しています。
多発性硬化症とヒトヘルペスウイルス6型Aに対する抗体との相関について
ヒトヘルペスウイルス6Aとヒトヘルペスウイルス6Bについて
小児期に発症する突発性発疹や成人期の帯状疱疹などの原因ウイルス”ヘルペスウイルス6”についての最近の研究報告がいくつか報告されていましたので調べてみました。
ヒトヘルペス6Bがうつ病の発症因子か?
ヒトヘルペスウイルス6Bとは小児に突発性発疹などの軽度の疾患を引き起こすウイルスという認識であり、ほぼ100%のヒトが潜伏感染しているウイルスというイメージでした。
しかし、ヒトヘルペスウイルス6Bが嗅覚の神経細胞に潜伏感染した場合にSITH-1遺伝子という遺伝子を発現し、この遺伝子が多いとアポトーシスを誘導しやすいことが報告されました。
マウスにおける実験では、SITH-1遺伝子を発現させると嗅球がアポトーシス(プログラムされた細胞死)を引き起こすだけでなく、脳内ストレスが上昇し、うつ病の症状であるショ糖嗜好性の低下が報告されました。またSITH-1遺伝子発現マウスでは不動時間の増加(うつ病様行動)が報告されており、抗うつ薬(SSRI)によって症状が抑制されることが報告されました。
さらにSITH-1遺伝子発現した“うつ病モデルマウス”では記憶を行う海馬の神経新生が低下していることが報告されています。
上記のマウスモデルを参考として、ヒトにおけるSITH-1遺伝子発現について特異的抗体を用いて検査した結果、SITH-1特異的抗体率は、うつ病患者では79.8%であったのに対して、健常者では24.4%しかありませんでした。また軽度のうつ症状がある人でのSITH-1特異的抗体率も健常者と比較して有意に高いことが報告されました。
以下は筆者らの推測を含みますが、過労状態では唾液中にヒトヘルペスウイルス6Bが増えることが報告されています。またヒトヘルペスウイルス6Bの増加は嗅覚系に特徴的に発現しているグリア細胞において、SITH-1を含む細胞からSITH-1が活発に作りだす可能性が示唆されます。つまり、仕事の緊張がうつ病を引き起こす要因としてヒトヘルペスウイルス6Bの増加に伴うSITH-1タンパク質の増加が要因となるのではないか?という仮説を筆者らの研究成果はサポートしているようにも見えます。
(疲れてていると体内のヘルペスウイルスが活性化して帯状疱疹を発症することがあります)

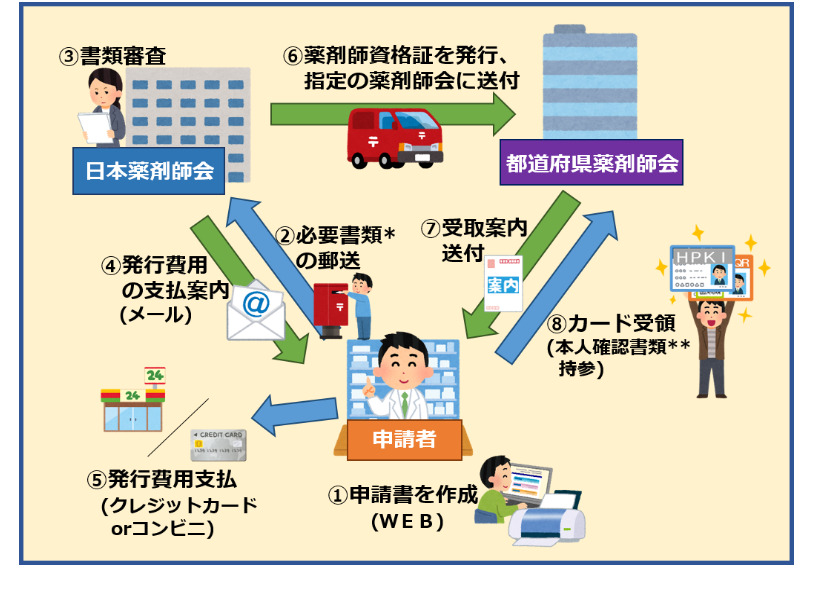
コメント